カテゴリー:1◆東洋美術史
-
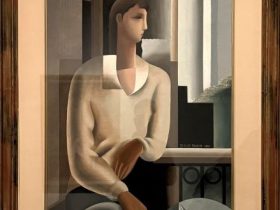
https://youtu.be/kyW8lsw4wn4?si=ioTHQBz3HArHClyE
窓の彼方に佇む夢
――東郷青児《窓》と詩的モダニズムの成立――
1929年に制作された東郷青児の《…
-

https://youtu.be/SX9371y-fuI?si=Xj8j8nTYfdLuRAPx
西洋婦人像静かな肖像に宿る近代の息吹
明治期日本美術の転換点を語るとき、黒田清輝という存在は避けて通れな…
-

https://youtu.be/eTe33KNTIMQ?si=glFlwbWj9lNDL39H
裸体・女(後半身)沈黙する背中が語る近代の始まり
明治二十二年、パリ。日本がようやく近代国家としての輪郭…
-

https://youtu.be/poAXkFNJ_zg?si=ME9MdIqarX-4EA30
黒田清輝《裸体・男(半身)》近代日本洋画が人体と出会った原点
明治維新以後、日本社会は急速な近代化の只中…
-
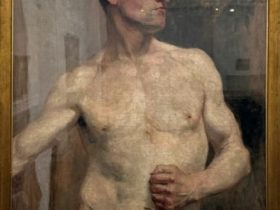
https://youtu.be/A4jryl1e8XY?si=MLHGm3cgsXIvOAe9
黒田清輝《裸体・男(半身)》をめぐって近代日本が人体と向き合った瞬間
黒田清輝の《裸体・男(半身)》(1…
-

https://youtu.be/oasrDtp9Zfc?si=D9FsnV-Tag4b3G9C
黒田清輝《羊を抱く少女》を読む近代洋画の胎動を宿す親密な肖像
黒田清輝の《羊を抱く少女》(1889年)は…
-
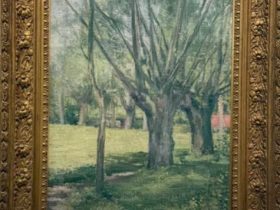
https://youtu.be/CnBp6Hpfq0g?si=jXrpRuIIHPiTnCm4
黒田清輝《楊樹》をめぐって
近代日本洋画が自然と出会った瞬間
日本近代洋画の成立を語るとき、黒田清…
-
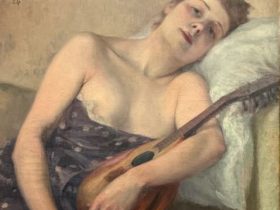
https://youtu.be/K6r9eholKn0?si=r8XNYj8e9AespvJF
マンドリンを抱く沈黙黒田清輝、フランス滞在期における内省の肖像
1891年、黒田清輝がフランス滞在中に描…
-

https://youtu.be/lxKgHeuN5fI?si=WjzIPYe3V7_IJqtk
黒田清輝 晩年の風景思想
《海辺の夏草》にみる静謐なる自然との対話
1916年(大正5年)に制作さ…
-

https://youtu.be/pBiREqFVFgI?si=i978ZNDEPuI-l1ty
黒田清輝と黄昏のまなざし
《濱辺の夕月》にみる外光派風景画の詩学
黒田清輝は、日本近代洋画の成立に…
ページ上部へ戻る
Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.
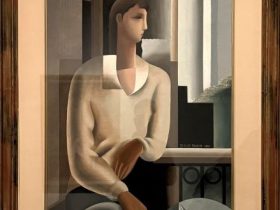



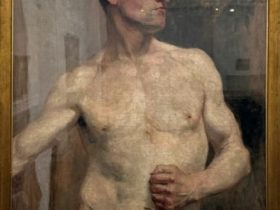

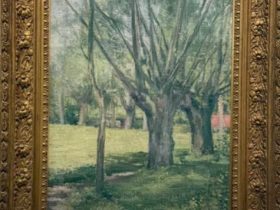
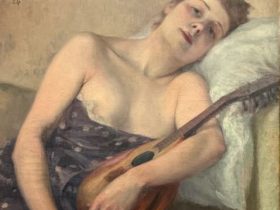



最近のコメント