タグ:静物画
-

https://youtu.be/W9Mnq1jiT2E?si=XLVPTmZkhsLlpln_
ギュスターヴ・クールベ《りんご》亡命者の眼が見つめた現実の静けさ
ギュスターヴ・クールベは、19世紀フラ…
-

https://youtu.be/i1vmkTbc1i4?si=64oIPlmwHnio_wbo
フィンセント・ファン・ゴッホ《ばら》苦悩の只中に咲く再生の静物
フィンセント・ファン・ゴッホが描いた《ば…
-

https://youtu.be/lmgZpq6BYoo?si=RtvdyYgI_9nRrNh_
花とウチワサボテンのある静物ルノワール転換期における沈黙の革新
オーギュスト・ルノワールが一八八五年頃…
-

https://youtu.be/UvbBtfwqHZw?si=gUIMRgX3Bg8U1eOp
色彩の祝祭ルノワール《菊の花束》にみる見る悦びと絵画の自由
1881年に制作されたピエール=オーギュスト…
-
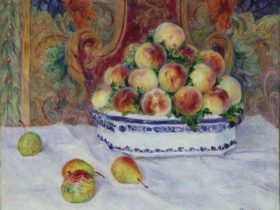
https://youtu.be/mOGFuAOY3Fw?si=dno5jN9PF-SMLCQW
ピエール=オーギュスト・ルノワール《桃のある静物》果実に宿る触覚と光──印象派静物画の到達点
1881年…
-
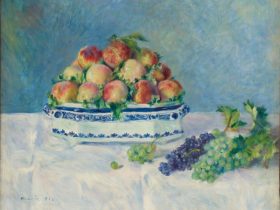
https://youtu.be/CnzbRSDqyP0?si=epZ0gGd6I_EBOY8P
桃と葡萄の静物―ルノワール、豊穣の色彩と静謐なる構成―
1881年制作の《桃と葡萄の静物》は、ピエール=…
-

https://youtu.be/1pfcbRPsKIw?si=jNq_03HjrRAUAAqo
沈黙する履物の肖像フィンセント・ファン・ゴッホ《靴》──物の奥にひそむ生の時間
静物画とは、本来、声をも…
-

https://youtu.be/JgIsCnAZQ-k?si=1WqI3KeQu56fbvYD
卓上に宿る永遠セザンヌ《リンゴとプリムラの鉢の静物》を読む
ポール・セザンヌが1890年前後に描いた《リ…
-

https://youtu.be/9hzBx66DgzQ?si=x1F7ZEVKswVN3Z48
リンゴひとつで、世界は揺らぐセザンヌ《リンゴと洋ナシの静物》における視覚革命
「リンゴひとつで、パリを驚…
-

https://youtu.be/XTCnvPnNfNw?si=afMts1RzFWpfwbHH
水差しとなすの静物沈黙する形態が奏でる視覚の秩序
ポール・セザンヌの静物画は、近代絵画における思考の実験…
ページ上部へ戻る
Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.




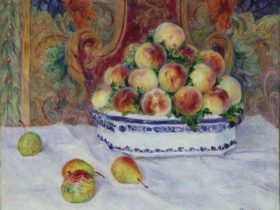
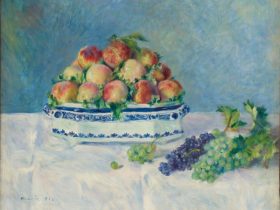





最近のコメント