カテゴリー:2◆西洋美術史
-

https://youtu.be/jSBi6aHSjc4?si=SVt8UGv1pi4Zs95U
マリアセンカ家族の記憶が肖像へと結晶する瞬間
マルク・シャガールの絵画世界を貫くものは、愛である。それは…
-
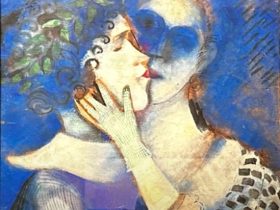
https://youtu.be/SDvztDVrtVg?si=EsNAh-kU9SrH6xu3
ブルー・ラバーズ青に溶ける愛の肖像
マルク・シャガールの絵画世界において、「愛」は単なる主題ではなく、彼…
-

https://youtu.be/f3uCztlVrrA?si=56FkRwR3Busi_THD
Vitebskの商店記憶が並ぶ場所
マルク・シャガールの《Vitebskの商店》(1914年制作)は、一…
-

https://youtu.be/IFLUceoaNBE?si=5vo3jEzfT3BsGuSn
散歩愛が重力を離れる瞬間
マルク・シャガールが1917年に描いた《散歩》は、彼の芸術世界の核心を、きわめ…
-
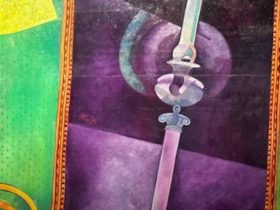
https://youtu.be/3Z6nEcjcSHM?si=Et4_BiJZk4eh1tn0
鏡夢と都市のあいだに立つシャガール
マルク・シャガールが1915年に制作した《鏡》は、彼の芸術における内…
-
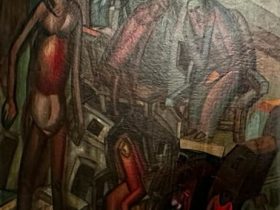
https://youtu.be/lnh8ElpWE9k?si=0a0tFxIhYj9ppU1l
失うものが何もない者たち――絶望の臨界点に立つ人間の肖像――
パーヴェル・フィロノフの絵画は、常に「人間…
-

https://youtu.be/K_QQf0uUDrE?si=AMzDa_x1oUPTOYKw
食卓の三人――沈黙の共同体と分断される近代――
パーヴェル・フィロノフの絵画において、日常的な場面がその…
-

https://youtu.be/i7lHQCiQtlg?si=lRrFEdq1X8hHkeN8
二つの頭――分裂する意識と全体性の肖像――
パーヴェル・フィロノフの作品世界において、「頭部」は特権的な…
-

https://youtu.be/cdN_RKo0X_k?si=MHToScfXBcSS3mG5
春の公式――パーヴェル・フィロノフ、生成する世界の絵画学――
ロシア・アヴァンギャルドのなかでも、ひとき…
-

https://youtu.be/nmJ6NLHjXQY?si=UZJlzTYLOmK86zxI
動物パンテイズムの眼差しと存在の連環
パーヴェル・フィロノフの《動物》(1925–1926年)は、彼の芸…
PAGE NAVI
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- 133
- »
ページ上部へ戻る
Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

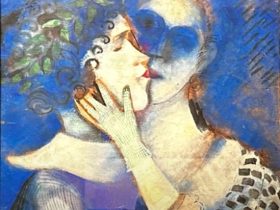


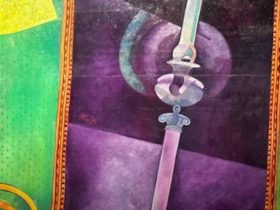
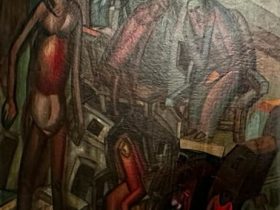





最近のコメント