【仏陀坐像】ミャンマー-コンバウン朝・18世紀-常設展-東京国立博物館-東洋館

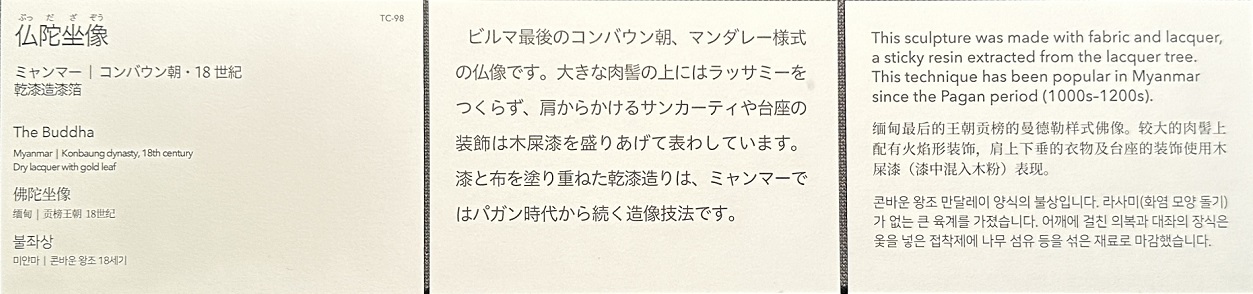
ビルマ最後のコンバウン朝、マンダレー様式の仏像です。大きな肉髻の上にはラッサミーをつくらず、肩からかけるサンカーティや台座の装飾は木屎漆を盛りあげて表わしています。漆と布を塗り重ねた乾漆造りは、ミャンマーではパガン時代から続く造像技法です。

ミャンマー(ビルマ)のコンバウン朝(1752年-1885年)は、ミャンマー史上の重要な王朝の一つです。コンバウン朝は、ビルマ人(ミャンマー人)の王朝であり、主にミャンマー中部と北部を支配していました。
18世紀のコンバウン朝における仏陀坐像については、多くの美しい彫刻作品が残されています。この時代には、ミャンマーの仏教文化が繁栄し、仏教寺院や仏教美術の発展が見られました。仏陀坐像は、仏教の開祖である釈迦(仏陀)が座った姿を表現したもので、仏教信仰の中心的な象徴として崇拝されています。
コンバウン朝期の仏陀坐像は、伝統的なビルマ様式の特徴を持っています。これらの像は、一般的に青銅や大理石などの材料で作られ、細部にわたる精巧な彫刻技術が特徴です。仏陀の顔は穏やかで優美な表情であり、仏陀が座る台座や背後には、複雑な装飾や文様が施されることがあります。
また、コンバウン朝期の仏陀坐像は、仏教美術の発展において他の文化の影響も受けています。例えば、タイのアユタヤ王朝やシャム(タイ)の美術様式からの影響が見られます。これは、当時のミャンマーと周辺地域との交流が盛んだったことを反映しています。
コンバウン朝期の仏陀坐像は、ミャンマーの仏教美術の重要な遺産であり、今日でもミャンマー国内外の美術館や寺院で展示されています。これらの像は、ミャンマーの宗教的・文化的なアイデンティティを示すものとして、人々に大きな尊敬と敬意をもって扱われています。




コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)






この記事へのコメントはありません。