
大沢昌助の《岩と人》
巨岩の前の静謐と謎
1940年(昭和15年)制作の大沢昌助《岩と人》は、第27回二科展に出品され、現在は東京国立近代美術館に所蔵される油彩作品である。その画面は一見、夏の日差しを浴びた開放的な屋外風景の一断面を切り取ったものであるように見える。しかし、構図の中心に鎮座する巨大な岩、登場人物たちの方向の定まらぬ視線、そして画面外に広がるであろう不可視の世界が、見る者の意識を絶えず外部へと導き、同時に「見えないこと」の意味を問いかける。そこに働いているのは、写実的描写と構図的制約、そして時代の空気が複雑に絡み合った、きわめて精緻な造形的思考である。
岩が遮るもの――構図上の軸
本作の最も顕著な特徴は、画面中央にほぼ垂直にそびえる巨岩の存在である。形状は単純化され、面の陰影によって量感を示しつつも、自然石に固有の複雑なテクスチャは抑えられている。そのため、岩は単なる自然物である以上に、構図上の「壁」として機能する。
この壁は、観者の視線を物理的に遮断する。私たちは岩の向こう側に男たちの姿があることを知るが、その全貌を知ることはできない。視線は遮られ、想像力のみがそこを越えて進む。古典的な遠近法的開放とは逆に、画面中央で空間が閉ざされるこの構造は、近代絵画における「遮蔽物の効果」の一つの極端な例といえる。
巨岩はまた、人物群を左右に分断する役割を果たす。左には少女と少年が並び、右奥には棒を持つ男たちがいる。両者の関係は視覚的には明示されず、岩の存在によってその距離感はさらに強調される。この分断は単なる空間的隔たりにとどまらず、心理的・物語的な断絶をも暗示している。
視線の交錯と「画面外」の存在
画面内の人物たちは、それぞれ異なる方向を見つめている。少女と少年は画面左外方に、右奥の男たちは岩の背後か、あるいは互いに視線を交わしているようにも見える。重要なのは、彼らの視線が決して観者に向けられていないことである。観者は物語の外部に置かれ、あくまでも第三者として、登場人物たちが注視する対象を追うしかない。
ここで興味深いのは、観者がその対象を「決して確認できない」構造が二重に仕込まれている点である。ひとつは岩によって視界が遮られることであり、もうひとつは画面外にある何かへの視線である。つまり、私たちは「岩の向こう」と「画面外」という二つの不可視領域を同時に意識させられる。この二重の不可視性が、作品の緊張感を著しく高めている。
光と色彩――朱色のワンピースの効果
強い日差しが、巨岩に濃い影を落とし、人物の肌や衣服をくっきりと浮かび上がらせる。特筆すべきは少女のワンピースの朱色である。この色は、岩の灰褐色や背景の淡い空色と対照的であり、画面の中で最も視覚的エネルギーを発する部分となっている。
この朱色は、単に人物を目立たせるだけでなく、物語的役割を担っている。夏の日差しを浴びた布地の鮮やかさは、健康的で快活な印象を与えるが、その一方で背景の不可視な出来事との対比によって、かえって不穏さや孤立感を感じさせる。光が強くなればなるほど、影もまた濃くなる――この明暗の対比は、本作の核心的なテーマとも響き合う。
肉体描写と古典的均整
大沢昌助は、戦前期の二科会で活動しながら、人体の量感や構造を重視する描写を一貫して行っていた。本作の少年や岩の向こうの男たちは、いずれも均整の取れた体付きで、古典的なプロポーションを備えている。筋肉の描き方は過度に誇張されず、しかし確かな骨格感を伴い、立体的に構成されている。
これは1930年代末から1940年頃にかけて、日本の画壇で顕著になっていた「古典回帰」の傾向とも通じる。すなわち、写実的精度と構成的安定性を求め、人物像に普遍的な美を付与する動きである。当時の社会情勢のもとで、この古典的均整は、国家的な理想像や健全な肉体美の表象と結びつきやすかった。そのため、本作における肉体描写は、単に画家の様式的選択にとどまらず、時代の思想的背景をも反映しているといえる。
棒を持つ男たち――行為の不明瞭さ
岩の向こうに立つ男たちは、長い棒状の道具を手にしている。しかし、それが漁具であるのか、測量器具の一部なのか、あるいはスポーツ用の道具なのかは判然としない。棒の用途が不明であることは、画面にもうひとつの謎を付け加える。もしそれが労働のための道具であれば、ここは作業現場であり、少女と少年はそれを眺めていることになる。もし遊戯や競技の一部であれば、場面の緊張感は別の意味合いを帯びるだろう。
この曖昧さは意図的である可能性が高い。具体的な行為が示されないからこそ、観者はその内容を自由に想像する余地を持つ。大沢はここで、写実的再現と物語的省略を巧みに組み合わせ、絵画における「余白の力」を引き出している。
1940年という時代の影
1940年は、日本が日中戦争の長期化に直面し、太平洋戦争開戦のわずか一年前にあたる。美術界でも国家総動員体制の影響が顕著となり、展覧会や作品制作は検閲や時局的要請と無縁ではいられなかった。二科会も例外ではなく、時勢に即した主題や様式が求められる空気が強まっていた。
このような時代背景のなかで、《岩と人》のもつ「古典的均整の人体」「自然の中の健康的な若者」というモチーフは、表面的には時局に適合する健全さを備えている。しかし同時に、視線の行き交いと遮蔽物による不可視の構造は、単純な健康礼賛にとどまらない複雑さを孕む。それは、当時の社会に漂っていた閉塞感や、不透明な未来への感覚を象徴的に反映しているようにも見える。
想像力の喚起――観者の参与
《岩と人》の本質は、見る者の視線を巧みに操作する点にある。巨岩は遮断と分断を行い、人物たちの視線は不可視領域を指し示す。観者は画面の外、岩の背後にある「何か」を探ろうとするが、決して確証にはたどり着けない。
この未解決感が、作品の余韻を長く引き延ばす。鑑賞後も、私たちの心の中で物語は続き、見えない対象を巡る推測が繰り返される。大沢は、視覚芸術が持つ「不在の力」を最大限に活用しているのである。
大沢昌助《岩と人》は、構図の中心に岩という「見えない壁」を置き、人物たちの視線の交錯と不可視領域の存在によって、観者の想像力を喚起する構造的な作品である。光と色彩の対比、古典的均整の人体描写、行為の曖昧さが重なり、画面には健康的な表層とその背後にある不穏な空気が共存している。
この作品は、1940年という時代の影を背景に持ちながらも、時代依存的なプロパガンダには回収されない複雑な視覚言語を内包している。見る者に問いを投げかけ続けるその力は、80年以上を経た今日においてもなお鮮やかである。
《岩と人》は、ただの風景や人物画ではなく、「見えないこと」「遮られること」の中にこそ、人間の経験の深みが潜んでいることを示す、静かながらも強靭な証言なのである。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)



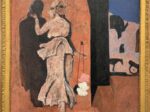
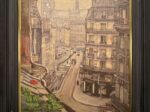

この記事へのコメントはありません。