タグ:自然
-

https://youtu.be/SkRGfkRzcZI?si=EzuOgYNKG7tOSRKi
「静けさの力──秋野不矩《桃に小禽》にみる戦時下の希望」1942年、絹の光に託された生命の祈り
19…
-

https://youtu.be/O0I6EWcb_RM?si=fw6WAhKSrm457BWK
存在の光を描く――髙島野十郎《田園太陽》にみる自然と人間の臨界孤高の画家が見つめた「光」と「生命」の形而上的風…
-
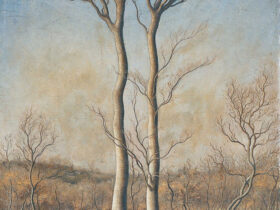
https://youtu.be/wtHR9cyqV8Y?si=Fc1Ji7vkE5kyAOkv
髙島野十郎《早春》──生命のうたう風景と光の予感自然と精神の共鳴を描いた若き日の生命讃歌
髙島野十郎(…
-

https://youtu.be/B5NYMCHF8zo?si=yRvN3i9K32khlRLY
光の化身としての自然――髙島野十郎《菜の花》に見る孤高の精神と永遠の光
髙島野十郎(1890–1975…
-

https://youtu.be/aR0dY_rZOFo?si=19gL1yww54YxwxCp
沈黙の光を仰ぐ
髙島野十郎《月》(1962)が映し出す、孤独と永遠のあわい
髙島野十郎は、近代日…
-

https://youtu.be/OItbSZy3vHE?si=UmCJ_cgdbhzhnaZi
月光の沈黙
髙島野十郎《満月》が映し出す、光と孤独の形而上学
髙島野十郎ほど、近代日本洋画史の中…
-

https://youtu.be/hFptDmPRJns?si=XvOnQAB_CGvfBzBI
海辺に咲く孤光――髙島野十郎《海辺の秋花》に見る沈黙と生命の詩学
髙島野十郎が描いた《海辺の秋花》(1…
-

https://youtu.be/EtvlJRXkHrY?si=RCEBdPqZj5JPOnMv
秋の花々 ― 髙島野十郎の沈黙する光
静謐な秋の午後のように、髙島野十郎の《秋の花々》(1953年)は…
-

https://youtu.be/zJwK7l_weds?si=y7Zen1jDQ9hinsxf
赤き果実の光──髙島野十郎《からすうり》にみる孤独と生成の美学
ひとつの果実が、これほどまでに深い精神…
-

https://youtu.be/UrcSByZK2j4?si=chbxG6H2XDM7kMl6
《昼寝》―陽光のゆらめきと、眠る身体の近代―
黒田清輝《昼寝》(1894年)は、一人の女性が草むらに身…
ページ上部へ戻る
Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.


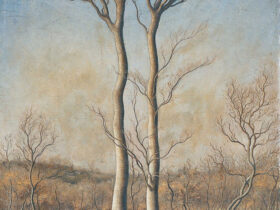








最近のコメント