過去の記事一覧
-

https://youtu.be/0MYAQXGg6_E?si=jMGlq7Iw7-oCDWk5
今中素友 金地に咲く祝意のかたち──紅白梅図屏風と大正期日本画の精神──
金地に咲き競う紅白の梅花は、見…
-

https://youtu.be/7OriJG_Jb0E?si=UwNxDguNWD_Bq_j2
伊藤若冲 桃花に宿る生命の律動──動植綵絵・桃花小禽図の静謐なる世界──
伊藤若冲の《動植綵絵》は、江戸…
-

https://youtu.be/6GF07_GuizU?si=BtINwaaixqCdzy4v
伊藤若冲 動植綵絵という宇宙──牡丹小禽図にみる生命観と絵画精神──
伊藤若冲の《動植綵絵》は、18世紀…
-

https://youtu.be/O9l-joZXTpw?si=hFGHEJCSRUfwA87U
幹山伝七と色絵磁器の近代──四季草花に託された明治の美意識──
明治時代前期、日本の陶磁器は大きな転換点…
-

https://youtu.be/hu4NAqGKo5A?si=DKM4sczyQvcl0gBq
萩に鴨図屏風――金の気配に宿る明治の秋――
《萩に鴨図屏風》は、明治時代に活躍した日本画家・永齋によって…
-

https://youtu.be/jMW5LHgOUxg?si=eVlTJeHwjX-5mU_A
菊花図額――陶磁に刻まれた写実と近代の気配――
明治四十三年頃に制作された《菊花図額》は、日本近代美術と…
-

https://youtu.be/jQqUDLzoqNA?si=D_njQ62IAAs9fb7j
背戸の秋図――私的空間に宿る季節の時間――
大正八年頃、伊藤綾春が描いた《背戸の秋図》は、近代日本画にお…
-
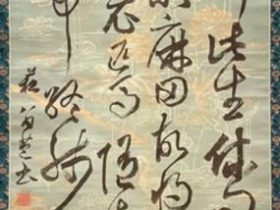
https://youtu.be/mTGrIVIdFwc?si=qpgofh8jkxnf1kFe
七言古詩――貫名海屋、詩聖の言葉を墨に託す晩年の境地――
江戸時代後期、日本の知識人たちは、中国古典に…
-

https://youtu.be/9AmVsD-vVuw?si=_B_m_fVGvaiSHmAo
加賀地方花鳥図刺繍壁掛――白山を織り上げる昭和初期皇室献上工芸の精神――
昭和初期、日本は近代国家とし…
-

https://youtu.be/K77p-18pH64?si=jqBbgywlg9ou6nWE
黒縮緬地乱菊模様振袖――昭和初期皇室服飾にみる染織美と祝儀のかたち――
昭和初期の日本は、近代国家とし…
ピックアップ記事
-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。
…
-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。
この像は、平安時代に作られたもの…
-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…
ページ上部へ戻る
Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.







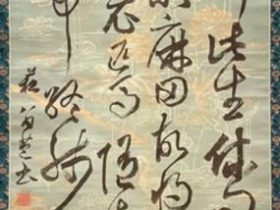






最近のコメント