過去の記事一覧
-

https://youtu.be/c4Js0L9dtso?si=-xvcyCexitFgfgD7
「桜花軍鶏図」(宋紫石、江戸時代・18世紀、紙本淡彩)は、江戸時代における絵画の中でも非常にユニークかつ写実的…
-

https://youtu.be/KA97Zky-9Kk?si=WBc8A7_-l7AxgmRx
「色絵桜樹図透鉢」は、仁阿弥道八による江戸時代後期の名作であり、京焼の代表的な作例の一つです。この作品は、江戸…
-

https://youtu.be/Axni-H5y4Is?si=QzwgbNoDnFE_7Y_U
「七宝四季花鳥図花瓶」(皇居三の丸尚蔵館所蔵)は、明治時代に活躍した七宝家・並河靖之の代表作として広く知られて…
-

https://youtu.be/FYls6iaaGeY?si=8gCCUGCWZAzRs4mn
「東方朔・梅尾長鳥・椿鳩図」は、江戸時代(17世紀~18世紀)の狩野常信(かのうじょうしん)による絹本着色の絵…
-

https://youtu.be/m_Nh_pqUvkU?si=B5wKRQu2QCKDPcN3
「裁縫筥並二道具」は、昭和3年(1928年)に製作された、非常に精緻で意匠豊かな裁縫道具セットであり、当時の日…
-

https://youtu.be/K77p-18pH64?si=jqBbgywlg9ou6nWE
この「黒縮緬地乱菊模様振袖」は、昭和5年(1930年)頃に制作された、日本の伝統的な衣装の中でも特に美しく、華…
-

https://youtu.be/9AmVsD-vVuw?si=_B_m_fVGvaiSHmAo
「加賀地方花鳥図刺繍壁掛」は、昭和3年(1928年)に制作され、皇居三の丸尚蔵館に所蔵されている貴重な美術品で…
-
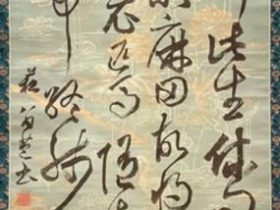
https://youtu.be/mTGrIVIdFwc?si=qpgofh8jkxnf1kFe
「七言古詩(貫名海屋)」は、江戸時代後期の儒学者であり、書家でもあった貫名海屋(菘翁、1778〜1863)によ…
-

https://youtu.be/jQqUDLzoqNA?si=D_njQ62IAAs9fb7j
「背戸の秋図」は、伊藤綾春によって大正8年頃に制作された絹本着色の絵画で、現在は皇居三の丸尚蔵館に所蔯されてい…
-

https://youtu.be/jMW5LHgOUxg?si=eVlTJeHwjX-5mU_A
「菊花図額」は、1910年頃に制作された陶磁製の作品で、現在は皇居三の丸尚蔵館に所蔵されています。この作品は、…
ピックアップ記事
-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。
…
-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。
この像は、平安時代に作られたもの…
-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…
ページ上部へ戻る
Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.







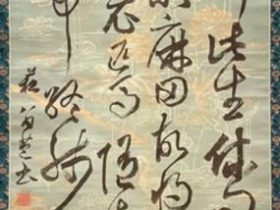






最近のコメント