過去の記事一覧
-

https://youtu.be/lNQny3MLw0A?si=EdYmkOEt9XT6XAqm
旭松岩上鶴図――朝暉に寄せる瑞鳥の黙想――
静謐な気配が画面を満たすとき、そこに描かれた鶴は、もはや単な…
-

https://youtu.be/WxQtksqa_no?si=FStdbMxDbmMqob5Y
七宝鳳凰図暖炉前衝立尾張七宝が結晶した祝祭と象徴のかたち
大正十四年、近代日本が伝統と革新のあわいに揺れ…
-

https://youtu.be/JN9bYAiPHzw?si=1Wtzi_yW2GhPpsQR
光を宿す瑞鳥――結城素明《鳳凰之図》にみる大正日本画の象徴と近代感覚
大正という時代は、日本美術史におい…
-

https://youtu.be/kVc6BQJ413Y?si=_e2emQ5pdwMwdiMX
寿のかたち、星の記憶――明治三十五年《寿老人置物》にみる近代日本工芸の精神
明治という時代は、日本美術に…
-

https://youtu.be/RBDDPK6bI_w?si=zrSeWiWB0odqG59a
岩上に宿る瑞祥――加藤龍雄《岩上鶴亀》にみる大正金工の精神
大正という時代は、日本美術において伝統と近代…
-

https://youtu.be/SxFUtmz56Q0?si=nxqDt6Rve5oEMgs0
岩上亀静止する時の寓意―大正金属彫刻に宿る長寿と秩序
大正十四年(一九二五)、近代日本がひとつの成熟期…
-

https://youtu.be/jkjRux__Evo?si=s0MRa6JgthHnCfVW
霊芝置物吹上の森に兆す不朽―瑞草を写した明治工芸の精神史
明治という時代は、日本が急速な近代化を遂げる一…
-
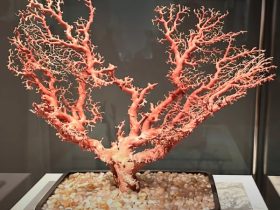
https://youtu.be/F0I7Ld4I53Y?si=O1_VlqmyvyAkTvbU
珊瑚樹鉢植置物海より生まれ、庭に根づく―宝石珊瑚が結ぶ自然と工芸
大正期の日本美術工芸は、伝統の継承と…
-

https://youtu.be/2bf__PiGl1A?si=o6hFgFDU3AZ8Kd_f
宝を載せて海を渡る大正日本の祝祭と地域の夢を映す宝船「長崎丸」
静かに、しかし確かな祝意をたたえて進む…
-

https://youtu.be/d3T0BsNHLHI?si=D-pF81qILZEt1QG9
狂える王の舞明治鋳金が宿した獅子の躍動と象徴
金属の肌に、今なお熱を帯びた動きが封じ込められている。明…
PAGE NAVI
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- 891
- »
ピックアップ記事
-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。
…
-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。
この像は、平安時代に作られたもの…
-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…
ページ上部へ戻る
Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.







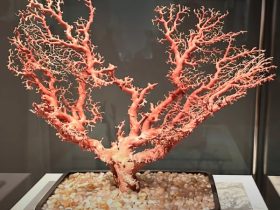






最近のコメント