過去の記事一覧
-

この豪華な小袖(袖口の小さな衣服)は、江戸時代に制作されました。生地には、刺繍と金箔が施されており、絹の平織り地に織り出しの浮糸模様が施されています。この小袖は、蜘蛛や海松貝のモチーフが施されており、自然界の要素が美し…
-

江戸時代の「観音菩薩・勢至菩薩立像」は、木製の彫刻で、漆塗り、金箔、切り金(切り鉄)と金属を用いて装飾されています。この立像は、観音菩薩(Avalokiteshvara)と勢至菩薩(Mahasthamaprapta)と…
-

唐時代(618年-907年)には、中国は文化と芸術の繁栄期を迎え、さまざまな美術品や工芸品が制作されました。その中で、「八棱金背銅鏡」は特に注目されるものの一つです。
「八棱金背銅鏡」は、八角形の形状を持つ銅製の…
-

この巻物は、室町時代に制作されたもので、釈迦牟尼(Prince Shakyamuni)が人間の苦しみを体験した後、宮殿生活を捨てる場面を描写しています。右下には、釈迦牟尼の父であるシュッダーダナ王(King Shudd…
-

酒を飲むための器です。内部にユーモラスな形の魚、縁に沿って4種の花文帯が刻まれています。表面に施されていた鍍金もかすかに残っています。ササン朝ペルシアの銀器は、シルクロードを経て中国や日本にももたされました。
サ…
-

平安時代に作成された金剛法菩薩坐像は、日本の仏教美術の重要な作品の一つです。この座った菩薩像は、銅製の彫刻で、仏教の密教における金剛界(こんごうかい)に関連するものとされています。金剛界は、天台宗の密教において重要な概…
-

「風俗美人時計 子ノ刻 妾」は、江戸時代の浮世絵師、喜多川歌麿(Kitagawa Utamaro)による作品です。この絵画は、彼が美人画の分野で活躍し、美しい女性たちを描くことで知られている中で制作されました。
…
-

「十二神将像の内」は、鎌倉時代に制作された作品で、木材に漆、色彩、金箔、または象眼を埋め込んで制作されたものです。この作品は、十二神将と呼ばれる神々の像が描かれたもので、これらの神々は薬師如来(Bhaisajyagur…
-

室町時代の唐花蒔絵鞍(Saddle: Gold maki-e with black lacquer decoration:Pommel: lacquered wood with gold and silver taka…
-
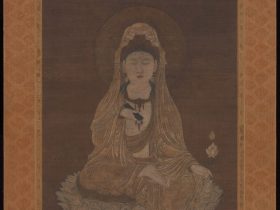
白衣観音図は、鎌倉時代に制作された観音菩薩(サンスクリット語:パンダラヴァシニ)の画像です。この作品は、観音菩薩の優美さ、尊厳さ、そして慈悲深さを強調しています。この図像は、密教仏教のアイコノグラフィから派生しており、…
ピックアップ記事
-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。
…
-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。
この像は、平安時代に作られたもの…
-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…
ページ上部へ戻る
Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.









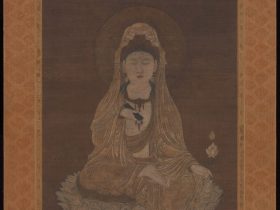




最近のコメント