過去の記事一覧
-
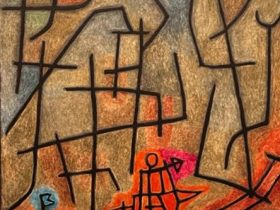
https://youtu.be/G3ZU8JTCoLE?si=yJBPjWyHT8eelGSB
山への衝動パウル・クレー晩年芸術における内的運動と時代の影
パウル・クレーの最晩年の作品群は、20世紀美…
-

https://youtu.be/6DHmT0lZcNs?si=iL0ri1dgsgrMFISN
集積の大地草間彌生 初期絵画における生成と世界感覚
1950年に制作された《集積の大地》は、草間彌生とい…
-

https://youtu.be/cq_C2c_KtXs?si=LePKIaacjG8VM2ns
作品66-1元永定正と1960年代日本抽象絵画の臨界点
1966年に制作された元永定正の《作品66-1》…
-

https://youtu.be/BKti8diVz-s?si=J6PqDL5pBIGZZ3e7
森へ行く日舟越桂と1980年代日本彫刻における具象の再発明
1984年に制作された舟越桂の《森へ行く日》…
-

https://youtu.be/xAdlKiLjp4k?si=gjjaCvS6hSD3VtZ2
大磯
――近代日本における〈休息〉の発見――
黒田清輝が明治三十年(一八九七)に制作した油彩画《…
-

https://youtu.be/FRdpwSiOUYE?si=N168Kbg798y28cGb
仁王捉鬼図
――狩野芳崖と近代日本画の臨界点――
狩野芳崖が明治十九年(一八八六)に完成させた《…
-
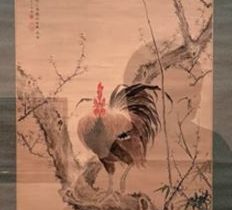
https://youtu.be/yQ9g5Pjl9r0?si=3S5sjBhtlWkCAFyz
闔家全慶
――明治南画における祝祭性と伝統の持続――
滝和亭が明治三十一年(一八九八)に制作した…
-
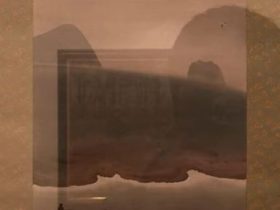
https://youtu.be/ze-HY-6jx7s?si=S488j73U2URnoa6I
朦朧の詩人菱田春草と林和靖の精神風景
菱田春草が一九〇〇年から一九〇一年頃にかけて制作した《林和靖》は…
-
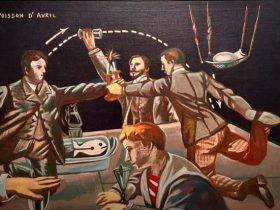
https://youtu.be/FTc7--UwFrM?si=TDiGSFb6hOlhwkmF
密室の笑い福沢一郎と理性の仮面
福沢一郎が一九三〇年に描いた《四月馬鹿》は、日本近代美術における前衛的…
-

https://youtu.be/TGphz1J6pXE?si=fhNp5CWBhaw_azvk
沈黙する大地飯田操朗と昭和初期の風景意識
飯田操朗が一九三五年に描いた油彩画《風景》は、日本近代洋画の…
ピックアップ記事
-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。
…
-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。
この像は、平安時代に作られたもの…
-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…
ページ上部へ戻る
Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.
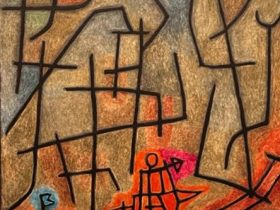





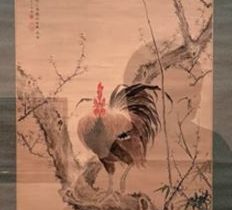
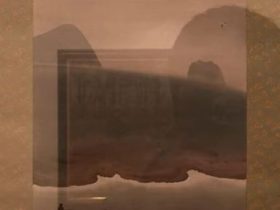
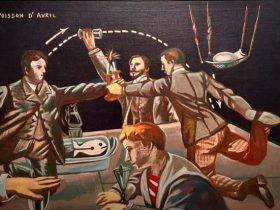





最近のコメント