カテゴリー:1◆東洋美術史
-
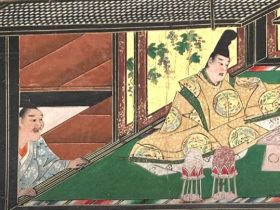
https://youtu.be/y9amkPgVDBk?si=uOhJnZzOpWgDtVCa
小栗判官絵巻 巻八上― 宴席に潜む運命の兆し ―
日本の絵巻物は、物語と絵画が不可分に結びついた総合芸術…
-

https://youtu.be/L5hYYMzdLhE?si=MWS2vUE5N8sh7xlh
寿老人松鶴竹亀之図― 明治皇室を寿ぐ吉祥画の精神 ―
明治という時代は、日本美術にとって大きな転換点であ…
-

https://youtu.be/bAPkbL_QNf0?si=q5oulHd9pQRmT_DF
蓬莱図理想郷を背負う山――狩野常信の神話的想像力
江戸時代絵画において、「蓬莱」という語が喚起するイメー…
-

https://youtu.be/Sxeku1ilcvw?si=nGUe2FBAJN3RXdBK
旭日波涛図 并 賛――昇暉と怒濤のあわいに書かれた精神――
荒々しくうねる波涛の彼方に、ひときわ静かな円…
-

https://youtu.be/lNQny3MLw0A?si=EdYmkOEt9XT6XAqm
旭松岩上鶴図――朝暉に寄せる瑞鳥の黙想――
静謐な気配が画面を満たすとき、そこに描かれた鶴は、もはや単な…
-

https://youtu.be/WxQtksqa_no?si=FStdbMxDbmMqob5Y
七宝鳳凰図暖炉前衝立尾張七宝が結晶した祝祭と象徴のかたち
大正十四年、近代日本が伝統と革新のあわいに揺れ…
-

https://youtu.be/JN9bYAiPHzw?si=1Wtzi_yW2GhPpsQR
光を宿す瑞鳥――結城素明《鳳凰之図》にみる大正日本画の象徴と近代感覚
大正という時代は、日本美術史におい…
-

https://youtu.be/kVc6BQJ413Y?si=_e2emQ5pdwMwdiMX
寿のかたち、星の記憶――明治三十五年《寿老人置物》にみる近代日本工芸の精神
明治という時代は、日本美術に…
-

https://youtu.be/VMY8TFETXGw?si=EdpVaf60sjVizLIP
霊獣の静坐江戸後期における麒麟香炉の造形と精神性
香を焚くという行為は、目に見えぬものと向き合うための、…
-

https://youtu.be/swfkmXjLr4U?si=qkQfhyOIMcrnIucE
黒田清輝 湖畔近代日本絵画が見た静かな夏の肖像
黒田清輝の《湖畔》(1897年)は、日本近代絵画の成立過…
PAGE NAVI
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- 242
- »
ページ上部へ戻る
Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.
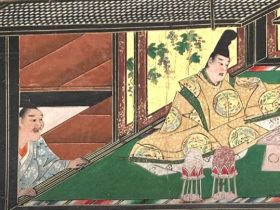










最近のコメント