カテゴリー:1◆東洋美術史
-

https://youtu.be/94f12P4TkKI?si=tqfuxCEuBQXyNejG
沈黙する都市の機構――松本竣介《N駅近く》に見る人間と社会の臨界点匿名化する群衆の中で、個の輪郭を探す
…
-

https://youtu.be/wHkKzwsOzbI?si=yvqZ6ILXdKHIOqvl
沈黙の青——松本竣介《黒い花》にみる都市の孤独と精神の風景透明な層の中に潜む声なき抵抗と、1940年代の青の寓…
-
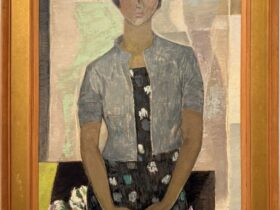
https://youtu.be/RrJIui-v_9w?si=SBtl8kzpj7tDriOD
静かに立つ光——深沢紅子《立てる少女》にみる戦後女性像の美学色と余白の呼吸が紡ぐ、ひとりの少女の内なる時間
…
-

https://youtu.be/9-AnRw80g5w?si=9e9LO32GnDAwWZNV
色の詩が聴こえる——甲斐仁代《秋のうた》にみる光と時間の層1959年、色彩の響きで季節を奏でた一枚の“うた”
…
-

https://youtu.be/R6wJgsTJ3ro?si=mrQIYPaVgooUcKcD
凝縮する存在——藤川栄子《塊》にみる形と精神の臨界点1959年、日本抽象絵画の転換点に立ち現れた“見る”と“感…
-

https://youtu.be/cbgDm4TqXWA?si=vy4ASNlovEWkFvIj
「色彩の静けさ――森田元子《想い》にみる戦後初期の女性のまなざし」
1947年、敗戦からわずか二年後に開…
-
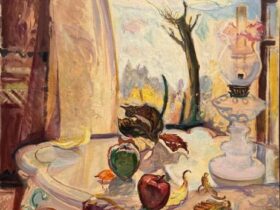
https://youtu.be/PU7ImfgSR9s?si=w3_sHV-R_twSAilc
「窓の向こうの再生――有馬さとえ《題名不詳》にみる戦後の呼吸」
東京国立近代美術館が所蔵する有馬さとえの…
-

https://youtu.be/VQXcjSkZHUA?si=Dmx0Ko5XDNuqRcVS
軽やかなる抵抗の絵画――桂ゆき《秋》にみる自由と遊戯の精神抽象と具象のはざまで揺れる、戦後前衛美術における女性…
-
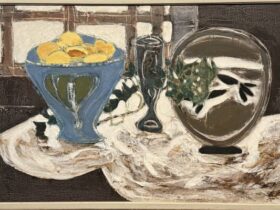
https://youtu.be/3nheapAoYqQ?si=7E3aYtSgxKdp2G_1
赤の記憶——三岸節子《静物(金魚)》にみる戦後洋画の再生-黒と白の狭間に泳ぐ生命、女性画家の眼差しが切り拓いた…
-

https://youtu.be/va4jwUqLYrs?si=l-75MWIDFdhS--fk
海の神話を超えて——竹内栖鳳《海幸》と近代日本画の臨界点-写生の精神と戦時下の美学が交錯する、巨匠最後のまなざ…
ページ上部へ戻る
Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.


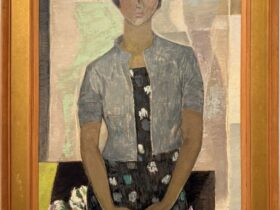



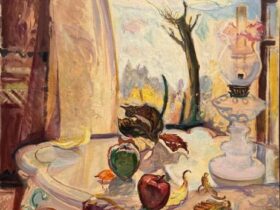

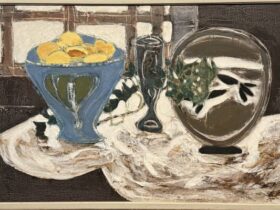


最近のコメント