カテゴリー:1◆東洋美術史
-

「鏨花鎏金銀剪」は、唐代(618年から907年)に中国で製作された剪定具で、銀製で部分的に金メッキが施されています。この作品は、7世紀から9世紀にかけての時期に位置しています。
剪定具は、主に紙や布などの素材を切…
-

「三彩陶枕」は、唐代(618年から907年)初期、具体的には8世紀初頭に中国で制作された陶製の枕です。この作品は、三彩(さんさい)と呼ばれる三色の釉薬が用いられています。
三彩は、黄色、緑色、褐色など異なる色調の…
-

「褐釉陶狗」は、唐代(618年から907年)に中国で制作された陶器であり、茶色の釉薬が施されています。この作品は、7世紀から9世紀にかけての時期に属しています。
陶器は、中国の工芸品が発展した時代である唐代におい…
-

「三彩馬夫俑」は、唐代(618年–907年)に制作された作品で、8世紀のものです。中国の文化に根ざしたこの陶器は、三彩釉(さんさいゆう)を施した陶器で作られています。
この作品は、馬と馬に乗った馬夫(馬を扱う者)…
-

この作品は、清代(1644年–1911年)に制作されたもので、「蓬莱仙境象徴小さな山々」と呼ばれています。中国の文化に根ざしたこの作品は、翡翠(Emerald)という素材で作られています。
作品の特徴的な要素は、…
-

「銀勺」は、中国の唐代(618年から907年)の作品で、8世紀に制作されました。銀製で、全長は約13インチ(33センチ)です。
この勺(しゃく)は、古代中国の食器の一種であり、銀で作られています。唐代において銀製…
-

「四神紋瓦當(白虎/朱雀)」は、中国の西漢時代(紀元前206年から紀元9年)の作品です。直径は約7 1/4インチ(18.4センチ)です。
この作品は、四神(四神獣)の一部である白虎と朱雀の紋章が彫刻された瓦當(が…
-
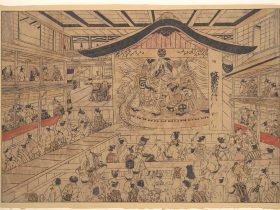
奥村政信の「紋尽名古屋曽我」は、江戸時代の1748年(延享5年)に制作された木版画(錦絵)です。作品は紙に墨と色彩を用いて制作されました。
この作品は横大判で、寸法は約12 x 7インチ(30.5 x 17.8セ…
-

この彫像は、江戸時代から明治時代にかけて制作されたもので、日本の文化を代表する作品です。木製の彫刻で、高さは約12.75インチ(32.4センチ)です。
彫像は、短い掛け衣と草鞋を身に着けた老人の姿を描いており、肩…
-
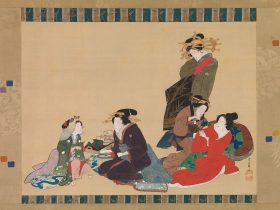
「五美人図」は、江戸時代の画家である蹄斎北馬によって1840年に制作された絵巻物です。この作品は、絹に墨と色彩を使って描かれた掛軸です。
作品は「五美人」と呼ばれる美しい女性たちを描いたものであり、それぞれが異な…
ページ上部へ戻る
Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.







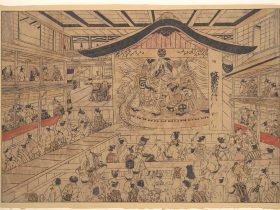

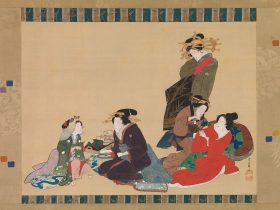

最近のコメント