カテゴリー:07・江戸時代
-

「江戸時代、金魚子地秋草図金具合口拵・付銀刀」は、江戸時代の短刀(短刀)であり、その装飾品と刃を含めて詳細について説明します。
製作者:宮田信清(Miyata Nobukiyo):この短刀とその装飾品は、宮田信…
-

「江戸時代、紅葉蒔絵鞘脇指拵」は、江戸時代の日本における刀剣の一種である脇指(Wakizashi)のための装飾品です。以下に詳細を説明します。
脇指(Wakizashi):脇指は、刀剣の一種で、刀に比べて短く、…
-

「秋草に鹿図鐔」は、日本の刀の装飾品である鍔(つば、Sword Guard)に関する情報です。以下に詳細を説明します。
製作者:紫原壽良画 Murasakibara Toshiyoshi:この鍔は紫原壽良画(M…
-

江戸時代、喜多川歌麿(Kitagawa Utamaro)による作品「母親と授乳中の子供」は、日本の浮世絵(ukiyo-e)として知られ、以下はその詳細です。
この作品は、喜多川歌麿によって制作された浮世絵で、制作…
-

江戸時代の短刀(脇指)の刃と装飾品については、以下のような特徴があります。
刃(は):江戸時代の短刀の刃は、通常は鋼鉄で作られ、非常に鋭利で強力でした。刃の形状やデザインはさまざまで、個々の刀匠(刀鍛冶)によっ…
-

江戸時代(1603年から1868年まで)における短刀(脇差し)の刃と装飾具(鍔など)は、日本の武士や刀剣文化における重要な要素でした。以下に、江戸時代に関連する短刀の刃と装飾具についての情報を提供します。
刃(…
-

「江戸時代、後藤家歴代揃目貫献上箱」は、江戸時代に存在した名門の工芸家である後藤家の刀柄の装飾品である「銘菸(めんすき)」を収めるための贈り物用の箱です。この箱は、後藤家が製作した刀柄の装飾品を一堂に収め、その収集品を…
-
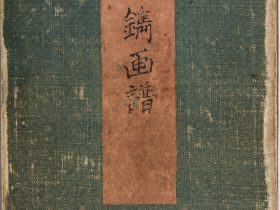
これは、刀装具職人である嵐山常行(Ranzan Tsuneyuki)の個人のスケッチブックです。このスケッチブックには、モノクロとカラーのペンとインクのスケッチ、既存の作品の図面が含まれており、これらはアーティストのモ…
-

花籠透鐔(はなごうとうつば)は、江戸時代の日本の刀装具の一種で、特に刀の鍔(tsuba)に関連するデザインスタイルや技法の一つです。この透鐔は、鍔が中空であることを特徴とし、その中に彫刻や切り抜きのデザインが施されてい…
-

江戸時代、木賊兎図大小揃物(Daishō Soroi-Mono)は、大小の刀(大刀と小刀、通常は太刀と脇差し)に関連する装飾具のセットを指します。このセットは、大小の刀に対応する守り手(鍔、tsuba)、小柄の柄(小柄…
ページ上部へ戻る
Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.







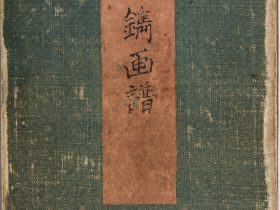



最近のコメント