喬 子一覧
-

https://youtu.be/4zH9N9xqZEQ?si=pOUvQaXtr4T70baF
眼のある風景見ることの深淵へ――視覚が風景を生成する瞬間
靉光が一九三八年に描いた《眼のある風景》は、日…
-
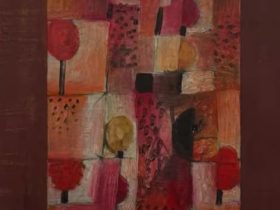
https://youtu.be/SYJd7XnllBM?si=i3DQofFwxeANHdhj
小さな秋の風景形と色がひらく内なる季節の構造
パウル・クレーが一九二〇年に制作した《小さな秋の風景》は、…
-

https://youtu.be/rGfMA-StcsA?si=7I_J3nUzJ5T7oKLO
1965(静物―緑と茶)抽象と自然のあわいにひらかれる静謐な構造
ベン・ニコルソンが一九六五年に制作した…
-

https://youtu.be/Us0IRa_jqwY?si=7xzMLJElXXaD2cLw
群落(A)岡鹿之助 色面が編む都市の静かな秩序
1962年に制作された岡鹿之助《群落(A)》は、都市とい…
-

https://youtu.be/0kO2C0yVq18?si=EjObph1NvK2oFOfi
貝殻と鳥脇田和 静謐の構図に宿る感情と思考
脇田和が1954年に描いた《貝殻と鳥》は、一見すると穏やかで…
-

https://youtu.be/b1sNFF50_cw?si=Tuvk7GxC9wCeSEzD
岩上の人野見山暁治 肉体と大地が交わる場所
1958年に制作された《岩上の人》は、野見山暁治の初期代表作…
-

https://youtu.be/uf7HRKJ6wpI?si=LSL9UDYYSQjPHqjd
CIRCLE-’70――円環にひそむ静かな宇宙――
オノサト・トシノブの《CIRCLE-’70》(19…
-
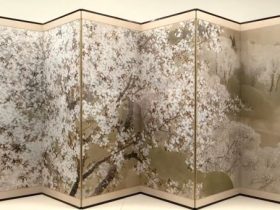
https://youtu.be/FRfaSALTZ5o?si=7Tj9fsR9l4i99_FA
小雨ふる吉野――白雲と花影のあわいに――
菊池芳文の《小雨ふる吉野》(1914年制作)は、日本画におけ…
-

https://youtu.be/Qwsakefj5CM?si=Z88Wp-iJMseTqJZH
草花図屏風――静かに息づく近代日本画の自然観――
藤井達吉の《草花図屏風》は、近代日本画が模索した新た…
-

https://youtu.be/OK312omVFv4?si=nSPiwZ6uSzNsRThb
縮緬地友禅花丸文着物 薰影――伝統の香り、現代の影――
森口華弘が1959年に制作した《縮緬地友禅花丸…
PAGE NAVI
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- 600
- »
ページ上部へ戻る
Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

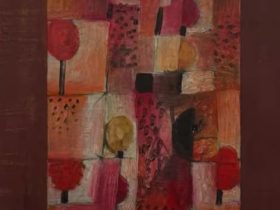





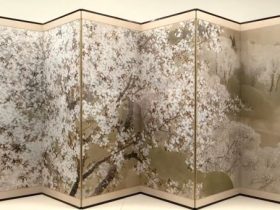



最近のコメント