喬 子一覧
-

https://youtu.be/MQmC9rLNUrI?si=2dNswKyIHbMeC_9P
花鳥図異国の色彩と江戸の感性が交差する張月樵の絵画世界
江戸時代中期、日本の絵画は静かに、しかし確実に変…
-
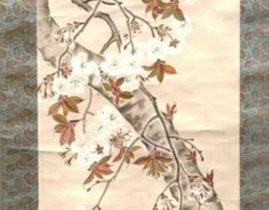
https://youtu.be/oUsYe3rvNN8?si=ur3-oskOuF5MG6-2
桜花図広瀬花隠がとどめた江戸の春の記憶
絹本に淡く咲き広がる《桜花図》は、江戸後期の絵師・広瀬花隠が、桜…
-

https://youtu.be/V2tcl2gzjTk?si=nqN_7vqHf3LfZpy4
漢武帝・西王母・長伯房図狩野探幽が描いた神話と帝権の交錯
江戸時代絵画の到達点の一つとして語られる狩野探…
-
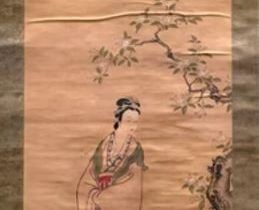
https://youtu.be/Vx43KWrnu1Q?si=7Gbn3Cexdtuojraz
唐美人図狩野常信が描いた異国の美と無常の詩情
江戸時代初期の人物画のなかで、《唐美人図》は、優雅さと静か…
-
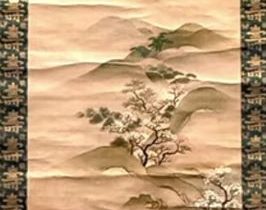
https://youtu.be/CEVOGayt5s8?si=xwTv60ZtFCuOod8X
吉野山区狩野永叔が描いた桜山水の精神風景
江戸時代中期の山水画のなかで、《吉野山区》は、自然描写の精緻さ…
-

https://youtu.be/vLXYCQTNAPk?si=t0rigvJ6w4qwsi3S
役者花見図宮川一笑が描いた春宴と江戸役者文化
江戸時代中期の都市文化が最も豊かに花開いた十八世紀、日本絵…
-

https://youtu.be/iHRPmGeMqes?si=NRgV2sk84DGD2ruA
勿来関図にひそむ風の記憶狩野栄信が描いた和歌的風景の深化
十九世紀江戸に描かれた「勿来関図」は、風景画で…
-

https://youtu.be/WKJ0YkAJTnQ?si=aslh9JO90SOhJf1I
伊勢物語絵巻 巻第二の詩的構造住吉如慶が描いた恋と時間のかたち
十七世紀江戸に制作された「伊勢物語絵巻 …
-

https://youtu.be/zNe9DWntIfw?si=EBKA2aDqh56vUQmU
春草図の静かな光村越其栄と江戸後期花鳥画の詩情
江戸時代後期の絵画において、「春草図」はひときわ静かな存…
-

https://youtu.be/-aDUavVq2vc?si=MaTIj0OR0iMQ8Q64
能狂言絵巻の視覚詩学徳川文化と舞台芸術を映す江戸のまなざし
江戸時代十八世紀に制作された「能狂言絵巻」は…
ページ上部へ戻る
Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

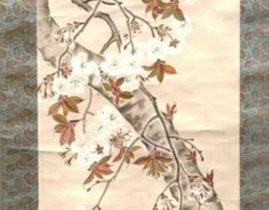

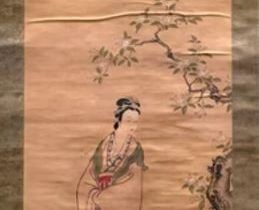
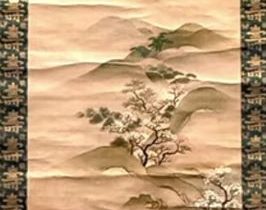






最近のコメント