
沈黙のなかの果実――《洋梨とブドウ》が映す、孤独と存在の光景
高島野十郎の静物画にみる、戦時下における凝視の倫理
それは一枚の静物画である。
だが、この《洋梨とブドウ》を前にしたとき、観る者はただの「果物」を見ているのではないと気づく。
この絵が静かに投げかけてくるのは、「見るとはどういうことか」という根源的な問いである。
果実たちは語らず、しかし沈黙の内に何かを強く訴えかけてくる。
その声なき声に応答するには、我々自身もまた沈黙のなかに降りてゆかねばならない。
高島野十郎という画家は、生涯を通してこのような沈黙と向き合い続けた。
彼は東京帝国大学の農学部を卒業後、安定した官僚の道を自ら捨て、画家としての孤独な道を選んだ。
展覧会、流派、画壇といった制度的な枠組みに与することなく、ひたすら「見る」ことを基礎にした絵画を生み出し続けた。
いかなる流行とも交わらず、誰かの期待にも応えず、ただ自分の目と、世界と、対象とのあいだにある緊張だけを信じて。
その徹底は、高島の代名詞ともいえる「蝋燭」シリーズに典型的にあらわれている。
しかし、《洋梨とブドウ》という果物を描いた一見ささやかな静物画においても、その孤高の姿勢は少しも揺らぐことはない。
果物は、西洋絵画において長いあいだ象徴的な存在であり続けた。
成熟と腐敗、生と死、時間の経過というテーマを視覚的に表すための格好のモチーフ。
カラヴァッジョ、オランダの静物画家たち、セザンヌ──多くの画家たちが果物に「語らせて」きた。
高島がこれら西洋の伝統にどれほど意識的に接していたのかは明らかではない。
だが、彼が西洋画法を学び、油彩という手法を選んだこと、そして対象を極度に凝視するそのまなざしの深さを見れば、
彼自身の静物画が、この長い歴史にある種の応答をしていることは否定できない。
《洋梨とブドウ》は、構図としては極めて簡素である。
中央に洋梨、その周囲に数房の葡萄が置かれ、果物たちは暗い背景のなかからぽっかりと浮かび上がる。
洋梨の皮には斑点やざらつきが繊細に描き込まれ、黄緑から黄土色への移ろいが、まるで一日の光の経過のように表現されている。
葡萄は深い紫色を帯び、ひと粒ごとに光のあたり方が異なる。
透き通るような粒もあれば、重く沈んだ影に溶け込むものもある。
だがこの構図は、食卓の悦楽や美的な飾り立てとはまったく無縁だ。
むしろ、異様なほどの静けさと緊張感が画面全体を支配している。
背景には一切の装飾性がなく、空間の奥行きさえも拒まれている。
そのため、果物たちはあたかも時間や場所といった具体的な文脈を剥奪されたかのように、
ただそこに、圧倒的な「存在」として、沈黙のなかに置かれている。
この光の扱いに、私たちは「蝋燭画」に通じる精神性を感じる。
《洋梨とブドウ》には蝋燭そのものは登場しない。
しかし、蝋燭の灯のような局所的な光──ただひとつのものを静かに、しかし鋭く照らすような光が、
ここでも果物たちの輪郭を明らかにし、同時にその孤独を際立たせている。
光は対象を祝福するものではない。
むしろ、それは「存在の重さ」を炙り出す手段なのだ。
果物たちは、ただ光にさらされ、あらわにされ、見られている。
そしてその視線を受け止めながらも、逆にこちらを見返してくる。
それは絵画においてとても稀な体験である。
我々が絵を見るのではなく、絵がこちらを見てくるような錯覚──
いや、それは錯覚ではなく、見ることと見られることの間に生まれる緊張が、
高島の筆によって極限まで高められているがゆえに起こる、ひとつの精神的現象なのだ。
そして忘れてはならないのは、この作品が描かれた時代背景である。
昭和16年、日本は太平洋戦争へと突入し、国民すべてが「国家のため」に動員されていった。
美術の世界もまた例外ではなく、多くの画家が戦争画を描き、戦意高揚に貢献することを求められた。
そのなかで、高島野十郎は戦争画を一切描かず、黙々と果物や風景を描き続けた。
この姿勢は、単なる無関心ではない。
むしろそれは、「描く」という行為の意味を根本から問い直したうえでの、静かな抵抗であったように思える。
果物を描くこと──それは一見、時代の要請にまったく応えない、無意味な営みのように映るかもしれない。
だが、《洋梨とブドウ》に込められた緊張と沈黙は、
まさに「声の大きい時代」に対する、もっとも純粋で倫理的な応答だったのではないだろうか。
爆音のなかにかすかに響く声、
喧噪にかき消されることを恐れず、
ひとつの果実の沈黙に耳をすますこと。
それが高島にとっての「描くこと」であり、
彼の絵が今もなお、観る者の心を震わせる理由なのだ。
技法的にも、《洋梨とブドウ》には高島の静かな意志が通っている。
油彩でありながら、彼の画面は極めて平滑で、筆致は痕跡を残さない。
まるで自我を消すように描かれたその筆遣いは、主観的な感情や技巧の誇示を排し、
対象とまっすぐに対峙しようとする意思の表れだ。
色彩もまた抑制されている。
華やかさや視覚的な快楽ではなく、
果物の皮膚に潜む「時間」や「老い」までをも感じさせる静かなトーン。
黄緑から黄土へと移る洋梨、
青黒く沈む葡萄、
そしてほとんど漆黒に近い背景──
すべてが沈黙を語っている。
高島にとって色とは、世界を美しく飾るための装置ではない。
色とは、対象がその場に在るという「痕跡」を刻印するための記号であり、
存在を可視化するための最低限の光なのだ。
《洋梨とブドウ》は、ただの静物画ではない。
それは「見ること」の根本に立ち返るための装置であり、
沈黙のなかで、存在の重さを問う精神の場である。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)



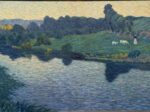


この記事へのコメントはありません。