【イタリヤの海 キオッジア漁村】髙島野十郎‐個人蔵

髙島野十郎《イタリヤの海 キオッジア漁村》――陽光の記憶としての出発点
「光の画家」が見た地中海の真実と、人間の営みの風景
髙島野十郎という名は、孤独と沈黙、そして「光」への果てなき探求を象徴する。晩年の《蝋燭》や《月》に見られる静謐な光の表現は、彼の画業を語るうえで欠かせぬ象徴であり、その名を不動のものとした。しかし、そこに至る以前、若き野十郎が異国の地イタリアで出会った陽光と色彩の体験を記録した作品《イタリヤの海 キオッジア漁村》を見過ごすことはできない。この一作は、彼の「光の探求」の萌芽が地中海の強烈な陽光のもとで芽吹いたことを示す、重要な起点である。
キオッジア(Chioggia)は、ヴェネツィア潟の南端に位置する小さな漁村だ。観光都市ヴェネツィアとは異なり、ここには日々の労働に根ざした生活の風景が息づく。アドリア海に面した港には、赭色(しゃしょく)の帆を掲げた漁船が並び、潮風と陽光が交錯する。野十郎がこの地を訪れたのは、1930年代初頭、ヨーロッパ留学の途上であった。彼はパリでアカデミックな写実教育を受けながら、フランス、ベルギー、イギリス、そしてイタリアを巡り、異国の風土と光を身をもって吸収していった。
《キオッジア漁村》の構図は一見、穏やかである。画面上部にはやや高めの水平線が引かれ、その下に海、漁船、家並みが層をなす。焦点は空や遠景ではなく、手前の港に置かれており、風景を通して人間の営みを描こうとする意識がうかがえる。そこには観光的な華やかさや耽美的な装飾はない。あるのは、陽光の下にさらされた生活の質感――それを、彼は真摯に見つめた。
茶褐色に染まった漁船の帆、石灰質の壁をもつ家屋、赤茶けた屋根瓦。それらのすべてが強烈な太陽光を受けて、輪郭を際立たせながらもどこか柔らかな陰影を宿す。野十郎の筆は緻密でありながら、過度な写実には陥らない。対象を「形」ではなく「光の質」として捉え、色面の関係性で風景を構築している。アドリア海の青は透明にして深く、赭色の帆がその中に強いアクセントを与える。白壁には淡い灰色の影が交差し、空の青白さと共鳴するように調和している。こうした色彩の組み合わせは、印象派のように瞬間の光を追うものではなく、むしろ物質のもつ永続的な「存在感」を際立たせる構成的なアプローチに近い。
この作品の核心は、やはり「光」である。だがそれは、後年の《蝋燭》に見られる内省的な光ではなく、「外界の光」としての太陽の輝きだ。海面には反射光が散り、波のうねりごとに銀色のきらめきが点々と浮かぶ。帆布には日差しの角度に応じた陰影が生まれ、空気の湿度までもが絵肌に感じられる。建物の壁も、光を浴びる面と影に沈む面とが呼応し、その反射が海に溶け込む。これらの描写は、単なる風景再現を超え、光そのものを「存在」として捉える野十郎のまなざしを予感させる。
彼がこの時期にヨーロッパで接したのは、単なる技法ではなかった。モネに代表される印象派の外光表現、セザンヌの構成的視覚、ゴッホの情念的な色彩――それらの影響を受けながらも、野十郎は「外光」そのものを模倣することには興味を示さなかった。むしろ、光を通して世界の「本質」に迫ろうとしたのである。キオッジアの陽光を浴びた漁村の風景は、彼にとって単なる異国情緒ではなく、光と人間生活の交錯する現実であり、その根源にある「永遠性」を感じ取る契機となった。
だからこそ、《キオッジア漁村》には「絵葉書的な美しさ」が存在しない。代わりに漂うのは、漁師たちの労苦の匂いと、生活の手触りだ。野十郎は日本人としての距離を保ちながらも、単なる観察者ではなく、土地に同化するように風景を見ている。異国の風景を「人間の営みが支える現実」として描く視線こそ、彼の芸術の独自性である。そこには、後年の孤高な画家像を予感させる誠実な観察と、対象への深い共感が息づいている。
晩年の《蝋燭》や《月》が内なる光を象徴するものであるなら、《キオッジア漁村》はその外的原点、つまり「外界の光」を全身で受け止めた体験の記録である。人工の炎や夜の月光を描く静寂の前に、野十郎は地中海の陽光の奔流に身をさらした。その強烈な感覚が、のちに「光の本質とは何か」という根源的な問いを生み出したのである。
この作品に漂うのは、若き画家の瑞々しい観察眼と、世界を知ろうとする純粋な欲求だ。だがその視線の奥には、既に「光の永遠性」を見つめる思想が芽生えていた。キオッジアの海で受けた光の記憶は、やがて静謐な炎や月光の中に結実していく。その意味で《イタリヤの海 キオッジア漁村》は、髙島野十郎の芸術的航海の「黎明」にあたる作品であり、彼の全生涯を貫く光の探求の第一章である。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)



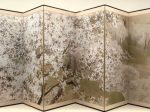


この記事へのコメントはありません。