【国光瑞色】広島晃甫(新太郎)ー東京国立近代美術館所蔵

「光の倫理──『国光瑞色』における静けさの構築」
1942年の絹本彩色が示す、祝祭と抑制のあいだ
1942年という年号を背負って生まれた日本画作品「国光瑞色」。その題名に響く音の質感は、すでに作品の運命を規定している。「国光」は国家的な光輝、すなわち時代のイデオロギーが託した輝きの象徴であり、「瑞色」は吉兆の徴を視覚化する色彩である。しかし本作の真価は、この言葉の華やぎや政治的響きを超えて、絵具と絹、光と余白が織りなす微細な倫理の空間にある。題名が先行して語る祝祭の気分を、画面がいかにして静けさへと反転させるか――その転換こそが、「国光瑞色」を今日まで思索に耐える作品にしている。
絹本という素材の選択は決定的である。絹の繊維は光を吸収し、また微かに返す。胡粉や岩絵具、膠が重なる層の下で、絹は常に内側から光を発している。したがって「光」は描かれるものではなく、素材に内在する現象である。絹の透過と反射のふるまいが、すでに画面の構想を形づくっている。絵具が乾くとき、膠が透明度を増し、絹の目がほのかに底光りを保つ。そのとき生まれるのは、派手さではなく沈静を帯びた輝度差――「瑞色」と呼ばれる清冽な明度の呼吸である。瑞色とは単なる色名ではなく、光が素材の内部で呼吸する速度のことなのだ。
この素材がもたらす抑制は、作品の倫理と結びつく。絹本彩色の伝統における「間」の概念――余白、薄塗り、にじみ――は、戦時下の鼓舞的レトリックを中和し、画面に静かな呼吸を取り戻す。題名に掲げられた「国光」が中心の輝きを暗示するとしても、その光は絹によって拡散され、余白に吸い込まれる。放射の図式がもし存在するなら、それを受け止めるのは淡墨の緩衝帯であり、視線の昂揚を「間」で制御する。ここに、日本画が持つ「形式による倫理」の核心がある。形式は単なる装飾ではなく、感情の高ぶりを抑え、観者の呼吸を整える規範として機能している。
「瑞色」は固定的な色調ではない。丹、緑青、群青、金泥、胡粉といった伝統的な顔料群が、松竹梅、鶴、鳳凰、旭光、波頭などの吉祥イメージと結びつき、歴史的に変化してきた総体を指す。その可変性は、色彩が象徴を超えて「関係」として立ち上がることを意味する。瑞とは色そのものの派手さではなく、異なる色と質のあいだに立ち現れる差異の気配である。対比と呼吸によって吉兆が生まれ、物質が意味を先導する。祝祭は装飾ではなく、物質の正確なふるまいによって支えられている。
戦時下の制作環境を思えば、絵具や金属粉などの物資は限られていた。だがその制約が、かえって技法の緊張を高めた。作者は彩度を上げる代わりに、粒子の粗密や層の厚みで光度を調整する。にじみと乾きの時間を制御し、地と色の距離で明度差を作る。その結果、画面に現れる「光」は観念ではなく現象としての光である。つまり「国光」は国家的スローガンの転写ではなく、絹と絵具のふるまいによって立ち上がる現象学的な光なのだ。ここにこそ、日本画が保持してきた「物質の倫理」が見いだされる。
近づいて見ると、胡粉の粒子が絹の繊維に絡み、膠の引きが微細な皺を作っているのがわかる。遠目には構成の秩序が支配しているように見えても、近づくほどに画面の呼吸は個体的で、時間を孕む。視線の速度はそこで減速し、観者は静かになる。題名が誘う昂揚を、絹本は受け止めない。むしろ視線をゆるやかに引き込み、祝祭の熱を沈める。そのとき、「瑞色」はもはや色彩の名称ではなく、視覚の速度が変化する現象そのものとして経験される。
「国光瑞色」は、近代日本画における「伝統と近代化」の緊張を一身に引き受けた作品である。伝統的な技法を保持しつつ、象徴を再構成する試み。松や鶴といった吉祥のモチーフが仮に描かれていたとしても、それは図像としての引用ではなく、呼吸を合わせた色と素材の関係として再設計されている。象徴は繰り返されるのではなく、再構築される。そこに近代の自覚がある。
祝祭とは、喧噪の中ではなく、沈黙の中で成立する。絹の繊維に絡む絵具の粒子、その粒が返すわずかな光、光を受け止める余白――それらがともに作り出すのは、声なき祝祭の場である。1942年という重い時代のただ中で、画面はなお静かであり続けた。その静けさは逃避ではない。むしろ、観念的な高ぶりを一度、物質の内部に還元する行為――それがこの作品の倫理であり、美術の根源的な力である。「国光」は観念としてではなく、物質の呼吸として再定義され、「瑞色」はその呼吸の速度に転化する。私たちはその速度に合わせて、ただ静かに見るだけでよい。そこに、戦時下の絵画がいまも私たちに開く通路がある。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)


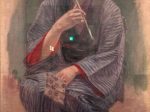



この記事へのコメントはありません。