【頬づえをつく女】ルノワールーオランジュリー美術館所蔵

肉体の光、精神の翳
ルノワール晩年の到達点としての《頬づえをつく女》──静謐と官能が交差する「存在」への凝視
2025年、三菱一号館美術館で開催される展覧会
「ノワール×セザンヌ ―モダンを拓いた2人の巨匠」
(オランジュリー/オルセー美術館コレクションより)
は、創造の根源を“構造”と“感覚”という二つの軸から照射する意欲的な試みである。その中で、オランジュリー美術館所蔵のピエール=オーギュスト・ルノワール《頬づえをつく女》(1910–1914)は、晩年のルノワールが到達した独特の光と肉体表現を象徴する作品として、会場の要となるだろう。本稿では、同作をルノワール晩年の「審美の行き先」として読み直し、20世紀美術へとつながるその意味を探ってみたい。
《頬づえをつく女》の画面に広がる柔らかな光は、ただ人物を照らすためのものではない。背景はほとんど抽象化され、色彩のゆるやかな層の重なりによって空間がかたちづくられる。そこに、頬、腕、指先といった身体の部分が、ほのかな光をまとった“発光体”として浮かび上がる。輪郭線はほとんど消え失せ、肌の曲面は筆触そのものの動きの中で立ち上がる。この“輪郭なき存在”は、晩年のルノワールが追求した絵画の本質を示している。
人物はわずかに俯き、指先を頬に添えて静かに佇む。だが、その内面を心理描写として読み取ることは不可能だ。画面の焦点は、モデルの具体的な人物像ではなく、彼女の身体が放つ“触覚的な存在感”にある。ルノワールは晩年、「形は色によって生まれる」という逆転した絵画観に到達していた。肌に重ねられた無数の色の層は、光と肉の感触を同時に宿し、観者の目と感性に直接触れるような透明度と質量を帯びている。
このような肉体表現への執着は、単なる官能ではなく、ルノワール自身の身体の痛みと切り離せない。晩年、関節リウマチにより指が変形し、筆を縛りつけて描いたという逸話はよく知られている。身体が思うように動かないなかで彼が追い求めたのは、「存在とは何か」を肉体そのものを通じて確かめる行為であったともいえる。モデルの頬に自らの手を添えるような、静かで確かな触覚。その感覚が画家の記憶と痛みを共鳴させ、画面に独特の温度を生み出している。
美術史的に見ると、《頬づえをつく女》はルノワール晩年が志向した「新たな古典主義」の核心に位置する。彼はラファエロやティツィアーノ、ルーベンスなど16〜17世紀絵画に惹かれ、“美しい人体”こそが絵画の永続性を支えると信じた。その結果、画面は一見柔らかく甘美でありながら、古典絵画に通じる構造的な安定感を備えている。光の層が形を生み、色が質量をもつ。この逆説的な表現は、20世紀初頭において極めて独創的であり、後のモダンアートの「平面」と「身体性」をめぐる議論にも接続する。
同展で並置されるセザンヌとの関係においても、《頬づえをつく女》の読みは深化する。セザンヌが風景を「自然を円筒・球・円錐で捉える」と語ったのに対し、ルノワールは自然も人体も“柔らかく息づく塊”として捉えた。セザンヌが構造の緊張を追い求め、後のキュビスムの源流となったのに対し、ルノワールは色と触覚の連続性を極め、官能と光の揺らぎを未来へと接続した。彼らは真逆の方向を向きながら、同じく「近代」を切り拓いたのである。
本作の女性像が纏う沈黙は、印象派の「瞬間の光」を越えて、永続する存在の気配をうちに秘める。頬に添えられた手は、思索というより、自らの存在をそっと確かめているようでもある。観者はその沈黙を前にし、光と肉体によって静かに形づくられる“生きていることの実感”に触れる。ルノワール晩年の作品にある深い慰撫の力、静かで確かな肯定は、まさにこの作品に凝縮されている。
2025年、三菱一号館美術館にて《頬づえをつく女》と対面することは、ルノワールが晩年に到達した「肉体への信仰」とも言うべき絵画哲学の核心に触れる体験となるだろう。光が形を生み、肉体が精神へと昇華する——その瞬間、観者もまた、自らの存在を静かに照らされるのである。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)

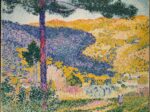




この記事へのコメントはありません。