【岩上の人】野見山暁治‐東京国立近代美術館所蔵

岩上の人
野見山暁治 肉体と大地が交わる場所
1958年に制作された《岩上の人》は、野見山暁治の初期代表作の一つとして、日本戦後美術の流れを語るうえで欠かすことのできない作品である。本作に描かれるのは、岩の上に身を預ける二人の人物像であるが、その主題は単なる人物表現にとどまらず、人間の存在そのものと自然との根源的な関係へと深く踏み込んでいる。画面を満たす肉体の量感と、大地のうねりのような風景は、静謐でありながら圧倒的な力を内包し、見る者を沈黙へと導く。
野見山暁治は、戦後日本美術のなかで「身体」と「風景」を一体として捉え続けた画家であった。1925年に福岡に生まれ、戦後間もなく画業を志した彼は、1949年に渡仏し、以後長くパリ郊外に拠点を置く。ヨーロッパの光と空気、起伏に富んだ土地の感触は、野見山の造形感覚を根底から揺さぶり、彼の絵画に独自の厚みと重力をもたらした。《岩上の人》は、まさにその体験が結晶化した時期の作品である。
本作において、人物は理想化された肉体でも、個人を特定する肖像でもない。太く簡潔な輪郭線によって囲われた身体は、骨や筋肉の構造を誇張しながら、同時に岩や丘陵と呼応する形態をとる。大きく誇張された手足は、労働や行為を暗示する以前に、大地に触れ、支え、踏みしめるための器官として存在しているかのようだ。人間はここで、自然に対峙する主体ではなく、自然の一部として描かれている。
人物が座す岩は、単なる舞台装置ではない。それは大地の凝縮された塊であり、時間の堆積そのものである。岩の質量感は、人物の肉体と拮抗し、両者の境界を曖昧にする。野見山の筆致は、岩と肌、丘と身体を同じ呼吸で描き分け、見る者に「人間もまた風景である」という感覚を静かに刷り込む。この感覚こそ、彼の芸術の核心であろう。
背景に広がる丘陵は、パリ郊外の風景を想起させるが、具体的な地名性は意図的に希薄化されている。柔らかな起伏を持つ丘は、人物の背後で静かに連なり、画面全体に持続的なリズムを与える。ここでは遠近法は厳密に追求されず、むしろ視線は画面の表層を滑るように移動する。風景は「眺める対象」ではなく、身体感覚として立ち上がってくるのである。
色彩もまた、本作の精神性を支える重要な要素である。野見山は、鮮烈な対比や装飾性を避け、抑制された色調のなかに深い響きを宿らせる。肌の色、岩の色、空と大地の色は互いに溶け合い、境界を曖昧にしながら、画面全体に厚い層を形成する。この色の重なりは、時間の堆積や記憶の層を思わせ、作品に静かな奥行きを与えている。
《岩上の人》が放つ力強さは、決して攻撃的なものではない。それは沈黙のなかに宿る力、存在そのものが持つ重さである。戦後の混乱と再生の時代にあって、野見山は声高な主張を避け、人間が大地に立ち返る姿を描いた。そこには、文明や理念を超えた、より根源的な「生」の感覚がある。
この作品はまた、野見山芸術における後年の展開を予告するものでもある。やがて彼の絵画は、人物像を離れ、風景そのものへと深化していくが、その基底には常に身体感覚が息づいている。《岩上の人》は、人間と自然が未分化のまま共存する地点を示す、ひとつの原点なのである。
《岩上の人》の前に立つとき、私たちは説明や物語を超えたところで、ただ「在る」ことの重みと向き合うことになる。野見山暁治が描いたのは、人間の姿でありながら、人間を超えた存在のあり方であった。その静かな迫力は、時代を超えて、今なお私たちの内側に深く響き続けている。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)

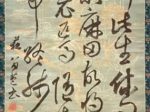




この記事へのコメントはありません。