【座って脚を拭う浴女】ルノワールーオランジュリー美術館所蔵

肉体の詩学としてのルノワール
ー《座って脚を拭う浴女》が示す、身体と光の再統合
ピエール=オーギュスト・ルノワールの晩年に至る裸婦表現は、単なる官能美の追求にとどまらず、「絵画とは何か」という根源的な問いへと接続する稀有な到達点を示している。印象派の創始者として若き日を駆け抜けたルノワールは、晩年に古典への回帰を志向しながら、自らの筆触と感性を鍛え上げ、独自の身体表現を生み出した。《座って脚を拭う浴女》(1914年) は、その探求の集大成に位置する作品であり、2025年三菱一号館美術館で開催される「ルノワール×セザンヌ ― モダンを拓いた2人の巨匠」において、あらためて現代の観者に問うべき強度を帯びて展示されることになる。
本作で何より目を奪うのは、脚を拭うという何気ない仕草が、絵画の内部で驚くほど豊かな動きとして響きあっている点である。モデルは前屈みになり、身体をやわらかくねじり、腕と脚を連動させる。そのポーズは一瞬の動作を切り取ったものに見えながら、実際には周到な構成の上に成り立っている。モデルの胴体から脚部へ、そして奥行きへと視線を導くルノワールの構図は、若き日の印象派的観察とは異なる、古代彫刻を思わせる彫塑的な秩序によって支えられている。
とりわけ注目すべきは、「肌の質感」が画面の中心をなす点である。晩年のルノワールは、肌の輝きを生み出すために円を描くような筆触を重ね、その表面に光が浸透するような色層を築いた。肌に宿るピンクやオレンジ、そこに潜む淡いグレーは、単なる写実ではなく、肉体という存在の時間と密度を可視化する装置のようである。光が肌に溶け込むこの描写は、ティツィアーノやルーベンスらの古典的裸婦の延長である一方、19世紀以降の色彩理論を吸収した独自のモダニズムにも通じている。古典と近代、触覚と視覚の融合が、この作品の奥行きを支えている。
《座って脚を拭う浴女》の背景には、布地や床の柔らかな色面が控えめに配され、人物の存在感を包み込む。ルノワールはこの背景を通して、空気が光を帯びて漂う「場の気配」を描き出している。セザンヌが構造化された空間を志向したのに対し、ルノワールは空間そのものを温度や湿度を帯びた生きたものとして扱った。この違いは、今回の展覧会の魅力を象徴する対比でもある。
本作が制作された1914年、ルノワールはすでに重度の関節リウマチを患い、指を曲げたまま絵筆を手に固定して描かなければならなかった。しかしその筆致は驚くほどしなやかで、若き日の軽やかさすら感じさせる。南仏カーニュのアトリエ「レ・コレット」で、陽光に満たされた空間の中、ルノワールは絵画に向かい続けた。身体の痛みと衰えに抗いながら描かれた裸婦像は、肉体そのものの美しさを讃えるだけでなく、「生きること」への執念にも似た輝きを帯びている。
20世紀初頭の絵画は抽象表現へと向かい、人体表現はしばしば古めかしいものとみなされた。その中で、ルノワールの裸婦像は時代と逆行するかのように、肉体の充実した重さと温度を描き続ける。しかし、この逆行は単なる懐古ではなく、むしろモダニズムが切り捨てた「身体」という根源を問い直すラディカルな姿勢である。触覚的でありながら視覚的でもある身体の在りようを、彼は絵画の中心に引き戻した。
《座って脚を拭う浴女》が今日においてなお新しいのは、そこに「絵画とは何を見せるものなのか」という問いが呼吸しているからだ。視覚の瞬間性と、触覚の永続性――その矛盾をどう画面に共存させるかという問題は、印象派以後の画家に突きつけられた最大の課題であり、ルノワールはそこに自らの回答を提示した。彼が求めたのは、モデルの個性を超えて、永遠の女性像としての普遍的な身体を描くことであった。
今回の展覧会で、本作がセザンヌの構築的な裸婦像と並置されることは、「モダンが歩んだ二つの道」を体験する機会となる。感覚とかたち、官能と構造、肉体と理性――その対比は古典的な議論でありながら、現代においてもなお有効である。観者は、ルノワールの浴女が静かに脚を拭うその瞬間、絵画史が抱える根源的な問いと再び向き合うことになる。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)



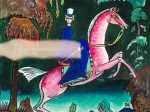


この記事へのコメントはありません。