【海】古賀春江ー東京国立近代美術館所蔵

海の表象学――古賀春江《海》にみる近代精神の交錯
均衡と夢幻が織りなすモダニティの風景
1929年に制作された古賀春江《海》は、昭和初期という文化的転換期を象徴的に映し出す作品である。東京国立近代美術館に所蔵される本作は、自然と人工、夢と現実が同一平面上で呼吸を交わすような、不思議な静謐と詩的密度を湛えている。そこに広がるのは、単なる海景でも幻想画でもなく、近代という時代の精神地図のような、象徴と構成が折り重なる複層的な空間である。
まず画面に支配的なのは、古賀が巧みに編み上げた「対称」と「対比」のリズムである。画面の右上には鳥と飛行船、下部には魚と潜水艦が配置され、自然物と人工物、空と海という二つの領域が鏡像のように対応関係を結んでいる。さらに画面端には、煙突と女性像がほぼ等しい垂直性をもって立ち現れる。これらは視覚的な秩序を構成するだけでなく、鑑賞者に「関係性の網目」を読み取らせる仕掛けである。それぞれのモティーフは単体では意味を持たず、他の要素との共鳴や対立によって初めて象徴性を帯びる。この精密なバランス感覚こそ、古賀春江の構成的特徴である。
タイトルが《海》でありながら、波や潮騒といった直接的描写がほとんど存在しない点も、作品の魅力を深めている。海はむしろ「深層」や「境界の曖昧さ」を象徴する装置として働き、そこに浮かぶ諸モティーフは夢状態の断片のように現れては消える。古賀が影響を受けたシュルレアリスム的手法は、ここで単なる奇抜さとしてではなく、構成的冷静さと結びつき、独特の緊張感を生んでいる。夢は幻想ではなく、むしろ透徹した思考の一部として画面に定着している。
とりわけ目を引くのは、右端に描かれた女性像である。ハリウッド女優グロリア・スワンソンの絵葉書を参照したとされるこの人物は、他のモティーフとは異なり、強いリアリティを保持したまま画面に佇む。彼女は海景の一部でありながら、どこか別の世界から切り取られた像のようでもある。その場違いな存在感が、逆説的に作品全体の「非人間的な構成性」を強調する。彼女の冷ややかな視線は、都市化する世界と人間存在の孤独を象徴する影のようにも読める。
さらに、飛行船・潜水艦・煙突といった機械的モティーフは、当時の都市文化の象徴であり、同時に未来への期待や不安を宿す記号でもある。それらは精密な写実ではなく、どこか玩具めいたデフォルメを含んでいる。機械文明は脅威ではなく幻影として現れ、夢幻的空間の中で柔らかく輪郭を曖昧にする。1920年代末の国際的な不安と希望、その両方が画面のなかに沈殿している。
《海》は、夢幻と構成、象徴と理性がせめぎ合うぎりぎりの均衡点に成立している作品である。古賀春江は幻想世界への憧れと、構成主義的秩序への関心を抱えながら、その二者を融合させる独自の視覚言語を獲得した。本作に漂う静けさは、単なる感情の停滞ではなく、時代の精神が描き出す「深い呼吸」のようなものだ。近代が抱えた矛盾や不安、そして微かな希望までもが、この海と名づけられた領域の中に封じ込められている。
《海》を眺めることは、ある時代の心象風景を読み解く行為であり、同時に現代の我々が見落とした「夢と構造が共存する世界」の在りかを再確認する営みでもある。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)



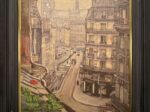


この記事へのコメントはありません。