【构筑物】村山知義ー東京国立近代美術館所蔵

都市断片の秩序学
村山知義《构筑物》が映し出す構築的モダニズムの深層
都市が震災復興と近代化の奔流のなかで形を変えつつあった1920年代──日本の美術史においてその時代は、前衛の意志と表現の実験が渦を巻く、きわめて特異な相貌を帯びていた。西欧の前衛思潮が濁流のように流入し、芸術家たちは既存の枠組みを破砕しながら、絵画・舞台・文学・建築など領域を越境する形で「新たな構造」を模索した。村山知義(1901–1977)はその最前線に立ち、舞台美術、劇作、絵画、批評など多岐にわたる活動を通じて、まさに「全方位的モダニスト」として1920年代の表現空間を先導した存在である。
その村山が1925年に発表したコラージュ的作品《构筑物》は、油彩に加えて紙、布、金属、木片、毛髪、印刷物など、日用品的素材を縦横に組み合わせて構成された、従来の絵画の枠を大きく逸脱する作品である。一見すれば雑然とした素材群が無秩序に寄せ集められているようにも見えるが、画面の基層には一貫した構築的思考が流れ、都市の断片を結び直すかのような厳密な秩序が潜んでいる。
作品を支える重要な柱となっているのが、画面に張り巡らされた「グリッド構造」である。この格子状のリズムはピエト・モンドリアンの新造形主義を想起させるが、村山の場合それは単なる造形的引用ではなく、複数の異質な素材をひとつの画面に導くための“思考の足場”として機能している。光沢とマット、硬質と軟質、印刷物と手仕事──それぞれが本来持つ物質性の差異は、この格子の秩序性によって緊張と協奏へと転化し、視線は画面内に方向性をもって誘導される。
特に、左上へ突き出した角材と中央に据えられた下向き矢印の関係性は、作品の構造的な主題を象徴する。角材は画面の外へと抜けてゆく垂直性を示し、矢印は重力や下降方向を示唆しながら、都市空間の流動性や情報動線を想起させる。これらは図像的記号であると同時に、物理的な重量感を伴って画面に介入する“構造物”であり、タイトル《构筑物》の意味をそのまま視覚化している。
こうした構成主義的アプローチは、村山が1920年代にベルリンで接触したロシア構成主義やバウハウスの芸術家たちの影響を強く反映している。タトリンやリシツキーらが掲げた「素材の真理を生かす」「芸術を社会的構造へ接続する」という理念は、村山の作品内部にも深く根を下ろしている。彼にとって芸術とは、感情の表出ではなく、世界の構造を可視化し、それを再編しうる知的営為でもあった。
《构筑物》の背景にある都市的文脈も重要である。関東大震災後の東京では、鉄道網、電灯、広告、百貨店、雑誌といったモダン文化が急速に拡大し、都市の視覚環境は断片と情報によって埋め尽くされていった。作品に貼り込まれた印刷物の切り抜き、金属片、日用品的素材は、そうした都市の匿名性や情報の氾濫を象徴する「都市の破片」であり、村山はそれらを素材として“都市そのものを再構築しようとする試み”を実践している。
この作品が示すのは、「断片を集めて構築する」というモダニズムの重要な命題である。バラバラの素材をただ並置するのではなく、そこに新たな秩序を見いだす行為こそが、村山の芸術観の核心にある。これは後年の舞台美術、出版活動、社会運動にも通じる、彼の一貫した思想的軸でもあった。
《构筑物》から100年を経た現在、私たちの世界も再び情報の断片化にさらされている。スマートフォンによる視覚の分散、モニターを介した現実の多層化、増殖する都市情報──私たちが生きる環境は、1920年代と同様に“断片の時代”である。だからこそ、この作品は現代においてより強い響きをもつ。村山は「完成された形」ではなく、「構築のプロセス」を提示し、鑑賞者を新たな構築行為へと誘う。作品の前に立つ私たちは、ただの観客ではない。断片をつなぎ、世界の構造を読み替え、再び構築し直す“共犯者”となるのである。
《构筑物》は、視覚実験であり、都市への応答であり、そして世界を再編するための思考の装置である。100年を経てもなお、村山知義が投げかけた「断片から秩序をいかに抽出するか」という問いは、私たちの足元に鋭く突き刺さっている。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)


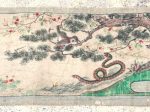



この記事へのコメントはありません。