【雪景色】佐伯祐三ー東京国立近代美術館所蔵

「沈黙の厚み——佐伯祐三《雪景色》にみる物質と感情の共振」
冬の白に刻まれた絵具の叫びと、1920年代パリの余響
東京国立近代美術館に所蔵される佐伯祐三の《雪景色》(1927年)は、一見すると静謐な冬の風景画に過ぎない。しかしその白い画面に身を浸すと、そこには単なる写実を超えた、絵画という行為そのものへの問いが濃密に沈殿している。厚く重ねられた絵具、ざらついた筆触、そして高く押し上げられた地平線——それらが織りなすのは「風景の再現」ではなく、「絵画の生成」を可視化した場である。ここにあるのは、雪景を描くことを通して、絵具という物質と感情という内的衝動とを一致させようとする、佐伯祐三の壮烈な格闘の痕跡である。
■ 高い地平線がつくる「静寂の緊張」
《雪景色》を前にしてまず感じるのは、画面構成の異様なバランスだ。地平線が極端に高く設定され、下方の大部分を占めるのは、何の陰影も持たぬ雪の野原——あるいは校庭のような、どこまでも平坦な地面である。そのため観る者は、自らが地面すれすれに立ち、白い空間の圧迫の中で息を潜めているような錯覚に陥る。
この構図は、偶然の産物ではない。佐伯は、渡仏期に触れたポスト印象派やフォーヴィスムの構図法を意識的に咀嚼している。特にヴラマンクやドランらが見せた、高い地平線と力強い前景による構造的緊張——その「圧」を、佐伯は自らの情動の座標軸に変換しているのだ。結果として、《雪景色》の画面は静謐であると同時に、内側から膨張するような張り詰めた空気を帯びる。
■ 絵具が語る——「厚塗りの同語反復」
本作の最大の見どころは、言うまでもなく雪の描写にある。白と茶、灰、そして鈍い青が幾層にも重ねられ、筆跡やナイフの跡がそのまま雪面の質感として立ち上がる。そこには、絵具の物質性そのものが主題化されている。佐伯は「雪を白で描く」ことを拒み、むしろ「雪=絵具」であるかのように、対象と媒材を同化させている。
この手法は、いわば「同語反復(トートロジー)」である。雪を描くために雪のように絵具を扱い、冷たさや湿り気を物理的な筆触で再現する。ここにおいて、描くという行為と描かれるものとのあいだの距離は限りなくゼロに近づく。絵画はもはや対象の再現ではなく、対象そのものの「もう一つの存在」として立ち上がる。
■ 「厚塗り=激情」——フォーヴィスムの系譜の中で
佐伯の厚塗り表現はしばしばファン・ゴッホとの関係で語られるが、《雪景色》においてはむしろフォーヴィスムの精神が鮮烈に響いている。フォーヴィスムは、感情の即発的な放出を筆致と色彩の暴発で表現したが、佐伯はその激しさを、日本的な内省の層に沈める。
ヴラマンクの冬景に漂う泥濘の重みや寒気の匂いは、佐伯の《雪景色》に通じる。だが、佐伯の筆致はヴラマンクの荒々しさとは異なり、どこか抑えきれぬ激情を雪の下に封じ込めるような、内爆的なエネルギーを湛えている。つまり、絵具は叫びであると同時に沈黙でもある——この二重性こそが、《雪景色》の最大の魅力である。
■ 冬というモティーフ——沈黙の中の不安定
本作に人物は描かれていない。あるのは、無人の雪原と、遠くに小さく見える建物のみ。だが、その「無」が語るものは多い。雪の下に潜む泥の気配、風の凍る音、あるいは画家自身の孤独。1927年、体調を崩しながらもパリで制作を続けた佐伯にとって、冬は単なる季節ではなく、心象の季節でもあった。
日本画における雪——たとえば横山大観や川合玉堂の淡墨の雪——が「静寂の美」として描かれたのに対し、佐伯の雪は重く、湿り、崩れ落ちる寸前の質量をもっている。これは、西洋油彩の技法を通して、日本的な風情の枠組みを意図的に拒否した試みであり、近代洋画の転換点を示すものといえる。
■ 絵具の時間——「厚塗り」が封じる瞬間
厚塗りの絵具は、乾くまでに時間がかかる。その間、絵具はゆっくりと沈み、ひび割れ、微かに色を変える。佐伯はその「変化の過程」までも絵画の一部として抱え込む。
雪とは、降り積もり、溶け、消える存在。厚塗りの絵具は、その儚さを物質として封じ込める装置となる。つまり、《雪景色》は、雪の一瞬の光景ではなく、「雪がそこにあった時間」そのものを層として保存している。筆致は時間の記録であり、絵画とは時間を厚く塗り込めた記憶体なのだ。
■ 結び——白の中の激情
《雪景色》は、冬の白に覆われた画面でありながら、そこには激しい感情のうねりが隠されている。高い地平線がもたらす構造的緊張、絵具の厚みが語る物質の詩学、フォーヴィスムの激情を内面化した筆触、そして冬という心象の季節——それらすべてが重なり、作品全体をひとつの「沈黙の叫び」に変えている。
佐伯祐三にとって《雪景色》は、単なる風景ではなく、絵画の存在そのものを問う応答であった。対象を描くことではなく、対象と同じ密度を生むこと。絵具の厚みは、画家の生命の厚みそのものだ。白と茶の対話は、冬の静寂と、燃え続ける情熱との共振であり、佐伯が短い生涯の終盤に到達した「沈黙の厚み」なのである。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)


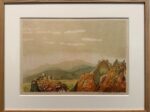
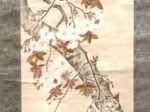


この記事へのコメントはありません。