【古羅馬の旅】山口薫ー川辺敏哉氏寄贈

山口薫《古羅馬の旅》——形と時間の交錯する静寂
古典への憧憬と現代へのまなざしのあいだで
1930年代、山口薫は長期にわたる滞欧生活の中で、画家としての根本的転換期を迎える。パリを拠点に、フランス、イタリア、スペインを巡りながら、彼は印象派的な外光表現から離れ、「形」と「秩序」への探求を深めていった。なかでも古代ローマやポンペイでの体験は、彼の造形観を決定的に変えた契機であった。彼は過去の遺産を単に模倣するのではなく、そこに宿る普遍的な構造と静謐な力を自らの絵画に再構築しようと試みた。その結晶のひとつが、《古羅馬の旅》である。
この作品の画面にまず目を引くのは、細部を極限まで削ぎ落とした構成である。大きな色面による静かな均衡、柔らかな輪郭で描かれた人物、そして背景と人物の境界が曖昧に溶け合う空間処理——これらはすべて、山口がヨーロッパの古典美術から学び取った比例感覚と秩序を、自身の現代的感性で翻訳した成果である。人物は壁の前に立つように見えながら、同時にその壁の一部であるかのように描かれ、現実と幻影がひとつの面の上に重ねられている。
この曖昧さは、単なる構図上の効果ではない。人物とその影、存在と痕跡、現在と過去——それらが同一の画面上で交錯し、時間の層を孕む空間が生まれる。まるで古代遺跡が時を経てもなお人の記憶に刻まれ続けるように、山口の描く人物もまた、形として留まりながら、過ぎ去る時間の中でゆらめいている。
色彩は抑制され、土色、鈍い青、くすんだオレンジといった沈着なトーンで統一されている。それはまるでポンペイの壁画の断片を思わせ、長い時間に風化された美を呼び覚ます。山口は光を直接描くことを避け、むしろ光の「残響」を描いた。画面全体に漂うくぐもった明るさは、時間の経過そのものが発光しているようであり、そこに「時間を凝縮する」彼の表現志向がはっきりと示されている。
1930年代後半、日本では古代ギリシアやローマを理想郷として描く作品が相次いだ。軍国主義の影が濃くなる中で、芸術家たちは現実の混沌から距離を取り、普遍的な美や秩序を古典に見出そうとした。山口の《古羅馬の旅》もまた、その文脈の中で理解されるべきだろう。しかし、彼の古典志向は単なる逃避ではない。むしろ、古典の形式と精神を媒介として、現代絵画の新たな地平を切り拓こうとする積極的な実験であった。
藤田嗣治が《ローマの風景》で装飾的構図と明快な線描による「古典の様式美」を提示したのに対し、山口はその明晰さをあえて避けた。彼が求めたのは、形と形の間に潜む「余白の感情」であり、存在の輪郭が滲む瞬間に宿る詩的な静けさであった。猪熊弦一郎のイタリア風景が旅の印象を即時的に描き出しているとすれば、山口の作品は時間を内側に沈殿させた静的な均衡を志向している。
この「静けさ」こそ、《古羅馬の旅》の本質である。画面に動きはない。しかしその沈黙の中に、過去と現在、理想と現実が交錯する振動が潜んでいる。人物が影と融合し、風景が記号のように整理されることによって、山口は絵画を「時間の場」として再定義しているのである。
彼にとっての旅とは、単なる地理的移動ではなく、精神的な遍歴であった。古代ローマの街道を歩くことは、芸術の原点をたどる行為であり、同時に自らの未来を照らす試みでもあった。《古羅馬の旅》は、その記録であり、永遠の未完の旅の証でもある。
やがて山口は帰国し、油彩や水彩でさらに形態の単純化と色面の調和を探求し続けた。彼の作品は、戦前日本の「古典回帰」潮流の中でも、最も内省的で形式的完成度の高いものと評価される。モダニズムの抽象化と古典造形の秩序を架橋するその姿勢は、日本近代洋画史において特異な位置を占める。
《古羅馬の旅》は、過去を描きながら未来を見据える絵画である。静謐な画面に漂うのは、時間の重みと人間存在の儚さ。その沈黙の中に、山口薫が見出した「絵画とは何か」という問いが息づいている。彼の旅は終わらない。古代ローマの石畳の上で、彼の影は今も揺らぎ続けている。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)




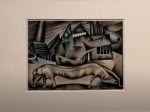

この記事へのコメントはありません。