【とり】麻生三郎ー大桑康氏寄贈ー東京国立近代美術館

静寂のなかの抵抗——麻生三郎《とり》に見る“見ること”の倫理
戦時下に描かれた一羽の鳥が語る、存在とまなざしの美学
麻生三郎の《とり》(1940年)は、一見すると控えめで、どこにでもいそうな小さな鳥の姿を描いた作品である。しかし、その静謐な佇まいの背後には、時代の空気を深く吸い込みながらも、それに抗うような精神の強度が宿っている。画面の中心やや上部に据えられた鳥は、具体的な種類を特定することが難しいほど抽象化されている。それは省略ではなく、対象の「形の本質」を掬い上げようとする鋭いまなざしの結果である。筆先が残すかすかな輪郭線や、光と影が曖昧に溶け合う羽の質感——それらがつくりだすのは、ただの写実ではなく、存在そのものの気配である。
背景は淡い灰褐色や青みがかったグレーの層によって構成され、空間的な奥行きや地平線を欠いている。そのため、鳥はどこにも属さず、宙に浮かぶように見える。現実の風景を描くのではなく、鳥が最も響く「場」を造形する——麻生の絵画に通底する構成的意識がここに現れている。観者は画面を前にして、鳥が存在する“空気”を感じ取るが、それは現実世界の再現ではなく、むしろ現実の“向こう側”へ誘うような視覚的装置である。
この作品が描かれた1940年、日本はすでに戦時体制の真只中にあった。美術界でも国策に沿った主題が求められ、戦争画や歴史画が隆盛していた時期である。そんな中で、麻生が「とり」という小さく非政治的な題材を選んだことは、明確な反戦表明こそしないものの、時代の同調圧力に対する静かな抵抗であったといえる。巨大な物語ではなく、身近な生命へと視線を向ける——それは“描く”という行為を通して、人間の感受性そのものを守ろうとする行為だった。声を荒げず、叫ばず、ただ一羽の鳥を見つめる。その沈黙のなかに、麻生の誠実な倫理が息づいている。
同時期の他の作品「男」では、人物の量感や陰影の強さを通して心理的な緊張が表現されている。それに対して《とり》は、筆致も色調も抑えられ、静寂が支配している。しかし、この静けさは弱さではない。むしろ、語らないことで対象の存在感を際立たせる強さをもっている。戦後の麻生が描く《子供》や《赤い空》にも、この“見ること”への誠実な姿勢が引き継がれていく。社会的テーマを扱うようになっても、対象を内面化し、そこから形を再構成する方法は変わらない。その起点が、まさに《とり》にあるのだ。
鳥というモチーフは、古来より自由、魂、旅立ちといった象徴と結びついてきた。しかし麻生の鳥は、そうした象徴性を意図的に避けているように見える。彼が描いたのは「普遍的な鳥」であると同時に、「この瞬間、この一羽」の個体である。その両義性こそが作品の魅力だ。画面に漂う筆のリズムや色のかすかな揺らぎのなかに、命の気配が息づいている。《とり》は象徴ではなく、存在そのものへのまなざしの記録なのである。
観者が絵の前に立つと、不思議なことに時間の流れが変わる。背景には空間的な手がかりがほとんどなく、光源も不明確なため、絵のなかでは「時」が停止しているかのようだ。鳥がこちらを見返すわけではないのに、その視線の方向が暗示的であるため、観者の目は自然とその“向こう”を探そうとする。画面上で視線が交錯する瞬間、わずかな時間の振動が生まれる。静止した絵画の中に、見る者の心が動く——その体験こそが麻生の狙いだったのかもしれない。
こうした絵画体験は、単なる美的鑑賞を超えて、「小さなものに目を向ける」ことの意味を思い出させてくれる。戦時下という巨大な暴力のただ中で、麻生は一羽の鳥を描くという“日常”を選び取った。その行為は、決して逃避ではなく、むしろ人間の根源的な感性への帰還である。大きな声が支配する時代に、小さな沈黙を選ぶこと——その勇気が、この絵の本質的な力を形づくっている。
麻生三郎《とり》は、今見てもなお新鮮で、深い余韻を残す作品である。筆致の柔らかさ、色面の呼吸、空間の曖昧さ——それらが一体となって、鳥を永遠のように画面上にとどめている。そこには、時代を越えて変わらぬ「見ることの倫理」が宿る。静かな絵の前に立つとき、観者は自らの視線のあり方を問われる。私たちはどれほど真摯に世界を見ているだろうか。麻生の鳥は、無言のまま、しかし確かにそう問いかけてくる。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)



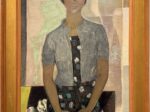
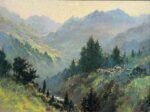

この記事へのコメントはありません。