【れんげ草】髙島野十郎‐個人蔵

髙島野十郎《れんげ草》――小さき花に宿る永遠の光
孤高の画家が見つめた自然と魂の共鳴
髙島野十郎(1890–1975)は、近代日本洋画史のなかで異彩を放つ存在である。画壇のいずれの団体にも属さず、名誉や地位を顧みることなく、ただ絵画そのものに向き合い続けたその生涯は、まさに孤高の修行者のようであった。彼の作品に通底するのは、徹底した観察と精神的な透明さであり、見る者を静かに圧倒する宗教的深度を持つ。その象徴的なモチーフとして知られるのが、炎を描いた《蝋燭》の連作や、夜空に浮かぶ《月》である。しかし晩年の彼が到達した境地をもっとも端的に示すのが、1957年に描かれた《れんげ草》である。
■ 名もなき花へのまなざし
レンゲソウ(蓮華草、ゲンゲ)は、春の田園に咲く素朴な花である。肥料として田に撒かれ、季節の移ろいとともにひっそりと消えていく。華美な装飾性や象徴性とは無縁のこの草花を、野十郎はあえて主題として選んだ。それは、絵画を通じて「ありふれたものの中に永遠を見る」彼の信念を体現する行為であった。
戦後、千葉県柏の農村に移り住んだ野十郎は、自給自足に近い生活を送りながら、自然と共に呼吸するように制作を続けた。都市の喧騒や流行から遠く離れ、彼が見つめたのは、足もとに咲く小さな花、風に揺れる草、田の水面に映る光だった。《れんげ草》は、そのような日々の中で生まれた作品であり、画家の精神が自然と融け合うようにして描かれたものである。
■ 静謐なる画面と生命の鼓動
《れんげ草》の画面には、数本の花茎が束のように立ち上がり、淡い緑と土の色の中に浮かび上がっている。背景は単純化され、視線は自然と中央の花に集まる。紫がかった赤の花弁は一枚一枚丹念に描かれ、茎や葉の深い緑と対照を成す。その色彩は鮮やかでありながらも、どこか抑制が効いている。派手さを排した穏やかな調子の中に、春の日の光が滲み出る。
筆致は極めて繊細でありながら、単なる写実ではない。輪郭は柔らかく揺らぎ、葉の影はかすかに震えるように描かれている。まるで花そのものが呼吸しているかのようだ。野十郎の筆は、対象の「形」ではなく「存在の瞬間」を描き取る。そこには、自然の生命を感じ取り、それを画布に定着させようとする祈りにも似た行為がある。
■ 光とともに生きる絵画
野十郎の作品を語るうえで欠かせない要素が「光」である。《蝋燭》や《月》に象徴されるように、彼は光を単なる物理現象としてではなく、生命の根源的な象徴として捉えた。《れんげ草》にもまた、春の日差しのような柔らかな光が満ちている。花弁に透ける光は、物質的な重さを超えて、存在そのものの純粋さを示している。
花の周囲には、見る者の心を鎮めるような静謐な空気が漂う。光は形を浮かび上がらせるだけでなく、空間そのものを呼吸させる役割を果たす。色彩もまた、赤紫と緑という補色の組み合わせが生み出す微妙な緊張によって、画面全体に生命の鼓動をもたらしている。その均衡は、まるで自然界の秩序をそのまま写し取ったかのようだ。
■ 「小さきもの」に宿る真理
レンゲソウは、華やかな花ではない。農民の生活に寄り添い、土の上で静かに命を全うする小さな植物である。だが、野十郎にとってそれは決して卑小な存在ではなかった。むしろ、無名の花の中にこそ、宇宙的な真理が宿ると信じていたのである。
彼がこの花を描いたとき、その姿は自身の生涯と重なっていた。画壇に背を向け、孤独に絵筆を握り続けた生き方。人に知られることを望まず、ただ純粋に「見る」ことの中に救いを見出した芸術家。その精神は、土の上で黙々と咲くレンゲソウの姿と重なり合う。《れんげ草》は、野十郎の自己像であり、また自然と人間との一体性を象徴する寓意でもある。
■ 絵画としての宗教性
野十郎は特定の宗教に帰依したわけではない。しかし彼の作品には、自然を通じて神の存在を感じ取るような信仰的感性が横たわっている。《れんげ草》の一枚一枚の花弁、葉の並び、茎の伸び――その全てに秩序と調和が宿ることを、彼は直感していた。それは「自然の中に神を見る」視線であり、同時に「人間の中に自然を見る」感覚でもあった。
こうした精神性こそが、野十郎の絵画を単なる写生の域から押し上げ、宗教画にも比すべき深みを与えている。そこに描かれているのは花そのものではなく、生命の本質であり、存在の根源である。
■ もうひとつの近代への道
戦後日本の美術界が抽象や前衛へと傾くなか、野十郎はあくまで具象の中に精神的真理を探った。西洋技法を用いながらも、日本的自然観と深く結びついたその表現は、近代日本洋画のもうひとつの正統を示している。《れんげ草》はその到達点であり、静謐な画面の中に潜む精神の強度が、時代を超えて見る者を魅了する。
■ 結語――静けさの中の永遠
《れんげ草》の前に立つとき、観る者は無言のうちに引き込まれる。そこには劇的な構図も技巧の誇示もない。ただ、春の陽光の中に佇む小さな花が、宇宙的な静けさの中で息づいている。野十郎が描いたのは、花ではなく「生きること」そのものだった。
小さなものを見つめる眼差しの中に、無限の広がりを見出した画家。彼の《れんげ草》は、現代を生きる私たちに、忘れかけた自然への信頼と生命への畏敬を思い出させる。画布の中の一輪の花は、今なお静かに、しかし確かに輝き続けている。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)



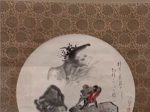


この記事へのコメントはありません。