【割れた皿】髙島野十郎ー福岡県立美術館蔵

割れた光の静物
―髙島野十郎《割れた皿》をめぐる沈黙の思索―
髙島野十郎の《割れた皿》を前にすると、まず訪れるのは「音のない崩壊」の感覚である。そこには劇的な破壊の瞬間も、感情の爆発もない。あるのは、ただ静かに割れてしまった器の姿だけである。白磁の表面をかすめる光は淡く、裂け目は乾いた空気の中で沈黙を保っている。その静けさは、戦後の日本が抱えた深い空白を、何より雄弁に物語っているように見える。
《割れた皿》は、敗戦から三年を経た1948年頃に描かれたとされる。日本の都市はまだ瓦礫に覆われ、人々は生きること自体に追われていた。そんな時代に、野十郎は再建の理想でも復興の希望でもなく、「壊れた器」を描いた。その選択は驚くほどに個人的であり、同時に普遍的でもある。壊れた皿は、彼自身の孤独を映すと同時に、戦後日本の精神的断絶を象徴している。
この絵の中には、いわゆる「静物画らしい」華やかさが一切ない。果物も、花も、装飾も、時間の流れを慰める要素はすべて排除されている。残されたのは一枚の割れた皿と、そこに射し込む淡い光だけである。だがその単純さこそが、見る者の心を深く抉る。皿のひび割れの一本一本が、まるで沈黙した叫びのように画面を走っている。
それは戦争の傷痕というより、むしろ「人間存在の傷」を象徴しているのではないか。修復されることのない断裂。そこにこそ、野十郎が見た「現実」があった。
皿は、もともと人が食を介して世界とつながるための器である。その皿が割れるということは、生活の基盤が崩れ、他者との共有の場が失われることを意味する。皿は「生の証」であり、その破損は「断絶の証」だ。野十郎はそれを悲劇として描いたのではなく、ただ「そうである」という事実として提示している。だからこそこの作品は、感傷を超えて、冷徹な現実感を放っている。
しかし、その冷徹さは同時に「光」を孕んでいる。皿の裂け目の縁に淡く宿る光は、どこか神秘的な質感をもっている。割れ目があるからこそ、光は複雑に屈折し、白磁の表面に微妙な陰影を刻む。そこには、「破壊の中にこそ光が生まれる」という逆説がある。野十郎が生涯追い求めた「光」は、単に明るさや希望を象徴するものではなく、存在を立ち上がらせる根源的なエネルギーであったのだ。
野十郎はかつて「自然そのものが光を発している」と語ったという。《割れた皿》においても、その信念は貫かれている。皿はもはや完全ではない。だがその不完全さの中に、光はより深く、より繊細に宿っている。割れた皿は、壊れた現実の象徴であると同時に、「なお光を受け止める存在」の比喩でもある。
それは、絶望と希望の境界線に立つ者だけが見いだすことのできる、静かな啓示である。
西洋のモダニズム絵画を想起するとき、この作品はセザンヌやモランディの精神にも通じる。彼らが日常の器物の中に永遠の形を探ったように、野十郎もまた、壺やグラス、皿といった無名の物体の中に「存在の光」を見ていた。だが決定的に異なるのは、モランディが調和と内省を追ったのに対し、野十郎は断絶と喪失を見つめたという点である。《割れた皿》の沈黙は、安らぎではなく、痛みの沈黙である。
日本的な美意識において「割れ」は、しばしば金継ぎの美へと転化される。だが野十郎の皿には修復の痕跡がない。それは「侘び寂び」の肯定ではなく、「修復不能な現実の凝視」である。彼は壊れた器を「美しい」とは言わなかった。ただ、「そこにある」ものとして描いた。その態度には、痛みを飾らずに受け止める誠実さがある。
画家は戦後、画壇から離れ、農村で孤独に暮らした。世間との接点を絶ち、絵を描くことと生きることがほとんど同義となっていった。《割れた皿》の前に立つとき、私たちはその孤独の深さを感じ取る。誰に見せるためでもなく、彼はただ描かねばならなかった。壊れた皿を通して、自身の存在のひび割れを見つめるために。
この作品には、「再生」や「救い」といった安易な言葉が入り込む余地はない。だが、光が皿の破片をそっと照らしていることを思えば、そこには確かに一筋の希望がある。それは声高な希望ではなく、沈黙の底にわずかに射し込む光――存在がまだここにあるという証としての希望である。
《割れた皿》は、絶望と希望の境界で光を描いた静物画であり、戦後の日本人が抱えた「失われたもの」と「それでも残されたもの」の両方を映し出している。
皿の割れ目に宿る光。それは、壊れながらもなお存在し続けるという、祈りにも似た肯定のかたちである。髙島野十郎の《割れた皿》は、静物でありながら、まるで人間そのものを描いている。沈黙のうちに息づくその光は、時代を超えて、今もなお私たちの内側で微かに瞬いている。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)


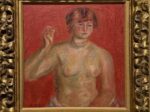



この記事へのコメントはありません。