【マダム・アンリ=フランソワ・リースネール】ウジェーヌ・ドラクロワーメトロポリタン美術館所蔵
- 2025/10/19
- 2◆西洋美術史
- ウジェーヌ・ドラクロワ, メトロポリタン美術館
- コメントを書く

「記憶の肖像——ドラクロワ《マダム・アンリ=フランソワ・リースネール》にみる時の余韻」
ロマン主義が描いた「喪失の予感」と「心の肖像」
ウジェーヌ・ドラクロワは、その劇的な筆致と鮮烈な色彩でロマン主義の象徴として知られている。だが彼の作品のなかには、激動や情熱の爆発とは異なる、静謐で私的な時間が宿るものがある。1835年に描かれた《マダム・アンリ=フランソワ・リースネール》は、まさにそうした作品の一つだ。この肖像画は、ただ一人の女性の姿を描くにとどまらず、時間の経過、記憶の蓄積、そして避けがたい喪失の影を私たちに感じさせる。ロマン主義絵画の表現の幅広さと深さを静かに物語る、極めて抒情的な一点である。
モデルとなったフェリシテ・ロングロワは、ドラクロワにとって義理の叔母であり、青年期から深い親交を持っていた人物である。彼女は若き日にナポレオンの寵愛を受け、華やかな宮廷生活の一端を担っていた過去をもつが、本作が描かれた時点ではすでにその華やかさを遠く後景に追いやっていた。ドラクロワは、そうした「かつての美」を飾り立てて再現することを選ばなかった。むしろ彼は、時間が刻んだ変化、人生が顔に残した痕跡を正面から見つめることによって、彼女の本質に迫ろうとした。
画面に現れる彼女は、控えめな衣服に身を包み、簡素な背景の中に落ち着いた半身像として浮かび上がる。目元には静けさと共に、どこか哀しみとも疲労ともつかぬ影が漂い、その眼差しは観る者をまっすぐに見つめる。その視線の奥には、彼女が歩んだ人生の豊かさと、いまこの瞬間を生きているという重みがにじんでいる。顔貌は過度に美化されることなく、しかし尊厳をもって描かれている。そこにあるのは「理想化された女性像」ではなく、「一人の女性の真実の顔」なのだ。
このようなアプローチは、同時代の肖像画家ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングルの作品とは対照的である。アングルが線と形態を通じて、永遠性や理想美を追求したのに対し、ドラクロワは光と影、色彩と筆触を駆使して、「生きられた時間」を描き出そうとした。つまり、彼にとって肖像画とは、過去と現在が重なり合う「記憶の容れ物」であり、「未来の喪失をあらかじめ悼む行為」でもあった。
実際、この肖像にはどこか「別れの予感」が漂っている。描かれた時点でマダム・リースネールは健在だったにもかかわらず、画面には不思議な哀感が満ちている。ドラクロワは彼女の姿を、ただ「生きている人」としてではなく、「やがていなくなる存在」として捉えていたのかもしれない。彼女の死後、ドラクロワがジョルジュ・サンドに宛てて書いた手紙の中で、「われわれの存在に不可欠な人々が一人消えるごとに、他のどんな関係によっても取り戻せない感情の世界がまるごと失われてしまう」と述べたことは、その感覚の深さを物語っている。
ここで描かれているのは、美の記録ではなく、「感情の記憶」である。ドラクロワの抑制された筆致と繊細な光の表現は、単に視覚的な肖像を超えて、彼女との関係性や、彼の中にあった思い出までもを画布に定着させている。これはまさに、個人的な愛着と歴史的記憶、両方の層をもった肖像画である。華やかな時代の名残を感じさせながらも、作品はきわめて私的な、家庭的な、そして精神的な空気に包まれている。
さらに、この肖像にはロマン主義の根底に流れる「メランコリー」の気配が濃厚に漂っている。人間の有限性、記憶の儚さ、そして芸術による時間の超越——そうしたテーマが、静かな表情と、抑えた色調の中に織り込まれているのである。彼女はもはやナポレオンの宮廷の華ではないが、その背後には時代の残像が薄く重なり、彼女自身もまた「歴史の一部」として存在している。ドラクロワは、そうした複数の時間軸を一つの画面に溶け込ませることに成功した。
今日、この作品はニューヨークのメトロポリタン美術館に収蔵されている。ドラクロワの壮大な歴史画に比べれば小品であるが、その内的世界の豊かさは決して劣るものではない。むしろ、このような親密な肖像画こそ、画家の人間観や感受性をもっともよく示すものと言えるだろう。
《マダム・アンリ=フランソワ・リースネール》は、記憶と喪失、そして人間存在のはかなさを描いた肖像画である。そこにはロマン主義が単なる情熱や劇性ではなく、内面的な深みと時間へのまなざしをも備えていたことが、静かに、しかし確かに刻まれている。画家の筆は、個人の肖像を通じて、時を越えて語りかけてくる。「一人の人間の消失が奪い去る感情の世界」を忘れまいとする、深い祈りのようなまなざしが、そこにはある。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)

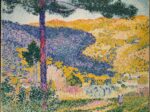




この記事へのコメントはありません。