【アブラハム・ベン=シモルの妻サアダと娘プレシアダ】ウジェーヌ・ドラクロワーメトロポリタン美術館所蔵
- 2025/10/19
- 2◆西洋美術史
- ウジェーヌ・ドラクロワ, メトロポリタン美術館
- コメントを書く

「静謐なるまなざし ― ドラクロワが描いた母と娘の肖像」
《アブラハム・ベン=シモルの妻サアダと娘プレシアダ》に見る女性像の個別性と文化的厚み
19世紀フランス美術において、女性像はしばしば社会や理念の象徴として描かれた。画家たちは女性の身体や姿勢、衣装を借りて、美徳や自由、感情の高まりといった抽象概念を視覚化しようとした。なかでもロマン主義の旗手として知られるウジェーヌ・ドラクロワは、《民衆を導く自由の女神》(1830年)において、女性を革命と自由の擬人像として描き、女性身体の劇的象徴化を極限まで押し進めた。
だが、1832年のモロッコ訪問を契機に制作された《アブラハム・ベン=シモルの妻サアダと娘プレシアダ》は、そのような劇的・記号的な女性像とは明確に一線を画す。ここには理想化も寓意もない。描かれているのは、ある特定の時間、特定の場所に生きる、ある母と娘の姿である。この作品は、ドラクロワが滞在中に出会ったユダヤ人有力者の家族をモデルに描いたものであり、当時の西欧美術において、異国の女性をこれほど静謐かつ個別的に捉えた肖像はきわめて稀であった。
画面の中央に配置されたサアダとプレシアダは、華美な演出からは遠い、簡素で落ち着いた構図の中に据えられている。母サアダは床に安定して腰を下ろし、白い厚布の衣装が静かな威厳を与えている。その衣には淡く青みがかった陰影が施され、静けさと成熟を静かに際立たせる。一方、立ち姿の娘プレシアダは、赤と金の衣装を身にまとい、若さと未来への期待を象徴している。その身体にはわずかな緊張が宿り、母に寄り添いながらも、どこか遠くを見つめるような眼差しが印象的である。
ドラクロワの筆致はここで装飾を自己目的化せず、それを文化的アイデンティティの媒介として用いている。白は清浄さと成熟、赤と金は生命力と華やかさといった色彩的記号が重ねられながらも、それらはあくまで人物の存在感を補完する手段として機能している。装飾や刺繍の緻密な描写は、美術的技巧の誇示ではなく、ユダヤ人女性の衣装に宿る文化的記憶と、個人の人生を背負ったものとして読むべきだろう。
特筆すべきは、二人の身体の「在り方」である。母の肩の傾き、手の置き方、視線の落ち着きに、家庭の中心を担う女性としての内面性がにじむ。対して娘は、やや硬さを残した姿勢ながら、今まさに母の庇護のもとから離れ、ひとりの存在として立ち上がろうとするような予兆を宿している。この微細な身体表現こそが、本作を単なる写実的肖像ではなく、心理的・文化的肖像たらしめている。
同時代の女性像の多くが、貴族的教養や市民的徳性を誇示するものであったことを思えば、この作品の異質性は明らかである。しかも本作は、当時の西欧に広まっていた「オリエンタリズム」の文脈にも関わっている。異国の女性たちは、しばしば官能的で幻想的な視線のもとに描かれ、実在の彼女たちではなく、ヨーロッパの欲望と幻想を映す鏡として機能していた。だが、《サアダとプレシアダ》には、そのような誘惑や演出が意図的に排除されている。ここにあるのは、他者を「記号」ではなく「個人」として捉える視線だ。
ドラクロワは、この母娘の肖像において、女性をただの主題とせず、歴史的・文化的コンテクストの中で生きる存在として描き出した。サアダの沈着な姿勢からは、家庭を支える母としての自覚と重みが感じられ、プレシアダの内に秘めたる緊張は、これから社会的役割を担っていく女性の曖昧で複雑な内面を予感させる。
本作は、女性を「理想」や「自由」の象徴として描いた他のロマン主義的作品とは異なり、個人の内面と文化的厚みを持った存在として捉えようとする、極めて稀有なアプローチである。そしてこのアプローチこそが、19世紀後半の印象派や写実主義による家庭内の女性像、日常に生きる女性たちの姿へとつながっていく先駆的試みだったとも言えるだろう。
《アブラハム・ベン=シモルの妻サアダと娘プレシアダ》は、19世紀フランス美術における女性表象のなかでも、静かに、しかし力強く異彩を放つ存在である。その筆致には、記号を超えた「他者」への敬意が宿り、女性の身体、衣装、関係性を通じて語られる物語が、見る者の心に深い余韻を残すのである。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)




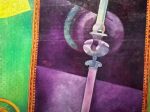

この記事へのコメントはありません。