
髙島野十郎の積る
白の奥行と静寂の深み
髙島野十郎(1890–1975)の画業を振り返るとき、まず強調されるのは彼の徹底した孤高の姿勢であろう。画壇に属さず、師弟関係やグループにも加わらず、ただひとり黙々と描き続けたその姿は、20世紀日本洋画史において稀有な存在である。生涯を通じて「光」を探究し、炎や月、太陽といったモチーフを繰り返し描いたことで知られるが、晩年の代表的な主題のひとつとして「雪」がある。今回取り上げる《積る》は、まさに雪のイメージを正面から扱った作品であり、野十郎の美学がもっとも凝縮された到達点のひとつといえる。
《積る》は、1948年(昭和23)以降に描かれたとされる作品である。戦後間もない混乱期、野十郎は再び郷里の福岡に拠点を移し、農村的な生活とともに制作を続けていた。そのなかで生まれたこの作品は、タイトルが示す通り「雪が積もる」という現象を主題としている。画面には、樹木や屋根、地面といった具体的な対象が薄く覆われてはいるが、それらは輪郭を曖昧にしながら一様に雪に包まれ、ひたすら白の広がりが支配する。鑑賞者の目は、描かれているものを「対象」として把握する以前に、白そのものが放つ気配に飲み込まれてしまう。
西洋絵画史において「白」はしばしば特別な意味を持ってきた。印象派の画家たちは光の分解を通じて雪景色を描き、モネは《雪の効果》や《アルジャントゥイユの雪》などで色彩の変幻を試みた。しかし、野十郎の白はそれとは異なる。彼の白は光学的な分析を超え、むしろ存在論的な問いを含んでいる。つまり「白とは何か」「雪とは何か」といった根源的な問いに近い。
《積る》における筆触は一見すると均質だが、よく見ると微細な色調の差異が折り重なっている。単なる白絵具の塗布ではなく、青みを帯びた白、わずかに黄を含む白、灰色がかった白などを幾重にも重ね、雪が空気や光を含みながら静かに沈殿していく様を描き出している。その表現は厚塗りというよりも、層を重ねることで「質感の深み」を生み出す手法に近い。結果として、雪はただの平面ではなく、奥行きをもった空間として現前する。
また、画面には時折、雪の隙間から対象物の痕跡がのぞく。例えば黒々とした枝の断片や、屋根の線などである。だがそれらは主役ではなく、むしろ雪の存在を際立たせるための対比にすぎない。全体としては「白」が画面を覆い尽くし、鑑賞者の意識を没入させていく。ここにおいて、野十郎の雪は「物質」でありながら「精神的空間」にも転化している。
《積る》が描かれた1948年以降という時期は、日本にとって深い傷を抱えた戦後復興期であった。焦土と化した都市、困窮する人々、未来への不安。そうした社会状況のなかで、雪という主題はどのような意味を帯びていたのだろうか。
雪は一方で「死」や「停止」を象徴する。生命の活動が止まり、自然が眠りにつく季節の象徴である。しかし同時に、雪は「浄化」や「新生」を示唆する。積もった雪がすべてを覆い隠し、やがて溶けて大地を潤すように、破壊を経て再生が訪れることを予感させる。戦争の惨禍を生き延びた野十郎が、あえて雪を描いたことは、そうした「停止」と「再生」の両義性を意識していたからに違いない。
加えて、彼自身の内的な孤独も反映している。戦後の美術界では抽象絵画や前衛運動が次々に登場し、国際的な潮流に接続しようとする動きが活発であった。しかし野十郎はそうした動向に背を向け、あくまでも自然のなかでの体験に根ざした表現を貫いた。雪に沈む静けさは、彼の芸術観と人生観を象徴的に示す舞台だったといえる。
注目すべきはタイトル《積る》そのものである。ここでは「雪」や「冬」といった名詞ではなく、「積もる」という動詞が選ばれている。これは極めて重要な選択であり、作品の解釈を方向づける。
動詞が示すのは「過程」である。雪は一瞬で積もるのではなく、時間をかけて少しずつ降り積もっていく。その過程の中に、時間の流れ、そして不可逆的な変化がある。つまりこの作品は単なる静止した風景ではなく、時間の堆積そのものを描いているのである。静止画でありながら、そこには無音の時間が刻まれている。この時間性の意識こそが、野十郎の絵画を詩的にしている所以である。
野十郎の代表作といえば《蝋燭》や《満月》《太陽》など、光を主題とした作品群である。炎の揺らぎ、月の冴え冴えとした輝き、太陽の強烈な白熱。それらはいずれも「光そのものを描く」という野十郎の美学の結晶であった。
その視点から見れば、《積る》における雪もまた光の表現であることがわかる。雪は単なる物質ではなく、光を反射し、拡散する媒体である。降り積もった雪は、日光や月光を柔らかく受け止め、時に青白く、時に黄金色に輝く。つまり雪は、光を最も純粋な形で受容する存在なのだ。野十郎が雪を選んだのは、光の探求の延長線上にあったともいえる。
とりわけ戦後の彼にとって、雪は「強烈な光」ではなく「静かな光」を象徴したのではないだろうか。戦前・戦中における彼の太陽や炎の絵が激しい求心力を持っていたのに対し、《積る》の雪はむしろ内省的で、沈潜する光を思わせる。そこには、激動の時代を経た画家がたどり着いた、ひとつの心の静けさが表れている。
《積る》を実際に鑑賞するとき、最初に訪れるのは「沈黙」である。音を立てない白の空間に立ち会うことで、鑑賞者自身の心の声が反響してくる。そこでは個人的な記憶、例えば幼い頃に見た雪の日の体験や、静かな冬の朝の感覚が呼び覚まされるだろう。野十郎の作品は観念的な説明を拒み、ただ「見る」ことを強いる。鑑賞者は画面と自分との間に沈黙の対話を交わすしかない。その意味で《積る》は、単なる視覚的な作品ではなく、体験的な作品であるといえる。
《積る》という作品が私たちに投げかけるメッセージは何だろうか。それは「積み重ねる」という行為の寓意である。雪が静かに積もるように、人の時間や経験もまた少しずつ蓄積していく。やがてそれは一つの風景をつくり、人生を形づくる。野十郎自身の孤独な制作もまた、まさに「積る」営みであった。日々の描写を重ねることでしか到達できない深みがあり、その果てにこのような静謐な世界が現れたのである。
《積る》は、単なる雪景の絵ではなく、「積もる」という現象を通して時間、存在、そして光の意味を問いかける作品である。戦後という混沌の時代を背景にしながら、画家が辿り着いた境地は、沈黙のうちに限りない普遍性を帯びている。鑑賞者はそこに、自らの内奥に降り積もる静かな雪を見出すだろう。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)

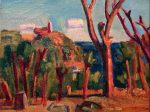




この記事へのコメントはありません。