
髙島野十郎の《さくらんぼ》
孤絶する光と果実の小宇宙
髙島野十郎は、その生涯の大半を孤独な制作に捧げた画家である。画壇に属さず、展覧会活動も最小限にとどめ、ただひたすらに自然の光と生命を描こうとした野十郎の作品群は、近代日本洋画の中で特異な位置を占める。《蝋燭》や《睡蓮》といった反復的な主題はよく知られるが、果物の静物画もまた、彼の画業において重要な一角を成している。
その中で《さくらんぼ》(昭和31〈1956〉年頃制作)は、単純な題材ながら、彼の光への執念と静謐な精神性が端的に結晶した作品として鑑賞に値する。リンゴや柿、ブドウといった果物を皿に盛り合わせて描いた他の静物とは異なり、この絵においては、鮮やかな赤の粒が純白の台の上に‐個人蔵直接置かれ、余白を大きくとった画面構成が際立つ。その簡潔さは、むしろ宗教画的な厳粛さを帯び、果実の存在を一層引き立たせている。
画面に置かれたサクランボは、房となって密集する粒と、ぽつりぽつりと散らされた孤立した粒とによって構成されている。この配置は偶然的な自然の散乱を模しているようでありながら、全体としてのバランスを精緻に計算していることがわかる。
密集と散在――そのリズムは単なる視覚的快楽を超えて、生命の充溢と孤独の対比を思わせる。群れをなす粒は豊穣の象徴であり、周囲に点在する粒は寂しさや孤絶の感覚を喚起する。そこには画家自身の生き方、つまり画壇や社会から距離を置き、自らの内なる光に殉じた人生が投影されているようにすら見える。
本作の核心は、鮮やかな赤い実そのものよりも、むしろそれらが作り出す「影」にある。サクランボの表皮はつややかに光を反射し、まるで小さな宝石のように輝く。しかしその一方で、房の茎や粒の重なりが生み出す影は極めて繊細で、かすかに台の上に滲むように描かれている。
光と影のこの拮抗は、野十郎が生涯追い求めた「光の真実」を如実に物語る。彼にとって光は単なる照明効果ではなく、世界を支配する根源的な原理であった。その光を最も純粋な形で捉えるために、彼はサクランボ以外の要素を一切排除し、白い台という「無」に近い背景を設定したのである。そこには、光と物質との交錯を純粋に提示しようとする画家の実験精神が明確に表れている。
サクランボの赤は、単なる写実的な果実の色彩を超え、生命の燃焼や一瞬のきらめきを象徴しているように見える。深紅から朱、あるいは淡い橙にまで変化する粒の色調は、光の当たり方によって微妙に異なり、画面に豊かなリズムを与える。
赤と白という二色の対置も重要だ。白い台は無垢の世界、あるいは雪の大地を思わせる。その上に置かれた赤は血潮のように際立ち、強烈な生の印象を残す。この二項対立の単純さは、日本的な「間」の美学とも共鳴し、西洋静物画の豊饒な量感表現とは異なる方向で、独自の精神性を帯びている。
解説にもあるように、野十郎はしばしば山形を訪れ、雪景色や羽黒山参拝を題材にしている。山形は言わずと知れたサクランボの名産地であり、彼が描く赤い粒の背後には、雪深い土地の自然環境や光の質が響いていると考えられる。
特に雪国の白とサクランボの赤という色彩の対比は、実際の風土のイメージに根ざしている可能性がある。冬の厳しさと夏の豊饒、その循環を象徴するように、《さくらんぼ》は単なる果物の写生を超え、四季の交替や自然の循環に触れる詩的な寓意を含んでいると見ることができよう。
この作品が描かれた1950年代半ばは、野十郎が千葉県柏市の田園に移り住み、ほぼ隠遁的な生活を送っていた時期にあたる。画壇からは遠ざかり、晴耕雨描の日々を重ねていた彼にとって、サクランボを白い台に一粒一粒並べて描くことは、世界との関係を最小限に絞り込みつつ、その核心を凝視する行為であったのではないか。
孤立した一粒のサクランボは、外界との断絶の中で生きる画家自身の姿を映し出すかのようであり、同時に、他の粒と共にあることによってかろうじて世界とつながろうとする存在でもある。その二重性が画面全体に静かな緊張感を漂わせている。
西洋静物画において果物は豊穣や富の象徴であり、ときに生命の儚さを示すヴァニタス的主題として描かれた。レンブラントやシャルダン、セザンヌに至る系譜は、物質と精神をいかに画面上で両立させるかという試みの連続であった。
野十郎の《さくらんぼ》もまた、この静物画の伝統を引き継ぎながら、独自の解釈を加えている。西洋のような量感的な描写ではなく、余白を活かした平面的で簡潔な構成は、むしろ日本絵画の精神に通じる。単独の果実を純白の上に置くという行為は、対象を象徴化し、観照の対象として提示する。そこには西洋的写実と東洋的精神性の接点が見出されるのである。
《さくらんぼ》を前にすると、観者はある種の沈黙に包まれる。鮮やかな赤は確かに目を引くが、それ以上に広がる白の余白が、見る者に静寂を強いる。そこには音も時間の流れもなく、ただ光と影だけが存在する小宇宙が広がっている。
この静けさは、野十郎の作品全般に共通する特徴である。《蝋燭》の微光や、《睡蓮》の水面に射す光もまた、沈黙を基調としている。《さくらんぼ》においてもまた、果実は声を発することなく、ただ存在そのものとして画面に居座る。その姿は、観者に向けて「見ること」の本質を問いかけているかのようである。
野十郎の信仰については多く語られてはいないが、彼の作品にはしばしば宗教的な響きが認められる。《さくらんぼ》もまた、単なる静物ではなく、赤と白の二項対立の中で、犠牲や救済、生命と死といった主題を暗示しているように思われる。
白い台は祭壇のごとく、そこに供えられた赤い実は供物のようである。果実の鮮烈な赤は血の色をも連想させ、生命の儚さや人間存在の有限性を想起させる。単純な題材を通じて、画家は存在の根源的な問いに迫っているのである。
《さくらんぼ》は、その簡潔な画面の背後に、野十郎の光への執念、自然観、孤独な人生、そして宗教的ともいえる精神性を秘めている。鮮やかな赤い粒は、ただの果物ではなく、光そのものを凝縮した結晶であり、存在の象徴である。
余白の広がる画面に浮かぶサクランボを見つめるとき、私たちは画家と同じように「見る」という行為の本質に触れる。光と影、群と孤、赤と白――そのすべてが静かに響き合い、沈黙の中で永遠の瞬間を示している。
この作品を前にしたとき、観者は単なる果物の美しさを超えて、存在の根源に接する。野十郎が孤独な日々の中で掴み取ろうとした「光の真実」とは、まさにこの小さな赤い果実に凝縮されているのである。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)


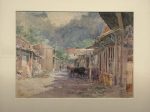



この記事へのコメントはありません。