
竹内栖鳳の《海幸》
近代日本画における伝統と時代の交錯
画題の重み
1942年(昭和17年)、竹内栖鳳は晩年の一作《海幸》を描いた。絹本に彩色をほどこし、精緻な筆触と豊かな色彩をもって描かれたこの作品は、東京国立近代美術館に所蔵され、近代日本画の展開を物語る重要な作例のひとつとなっている。タイトルの「海幸」は、日本神話における「海幸彦・山幸彦」伝承を想起させる。大海原に漁に出る者、あるいは海の恵みを受ける人々の姿に、日本古来の自然観と神話的寓意とが重なり合う。その意味で《海幸》は、単なる風俗画ではなく、神話的根源を意識した文化的メッセージを含んでいるといえる。
制作年の1942年は、日本が太平洋戦争に突入して一年を経た緊迫の時代であった。国民美術展や紀元2600年記念美術展が開催され、絵画にも国威発揚的な要素が求められるなかで、栖鳳はこの「海幸」を描いた。彼が生涯にわたり追求した「写生」と「装飾性」の調和が、戦時下という特殊な文脈の中でどのような意味を帯びたのか、そこに本作の批評的意義がある。
竹内栖鳳の画歴と美学
竹内栖鳳(1864–1942)は、近代日本画を代表する巨匠である。京都画壇に学び、四条派の伝統を受けつつ、洋画的な写実を取り入れた「動物画」の名手として知られる。獅子や虎から猫、鳩に至るまで、あらゆる生き物を精緻な観察と独自の筆法で描き、対象に生気を宿すその筆力は圧倒的であった。彼はまた、西洋絵画を積極的に吸収し、日本画の革新を図った人物でもある。明治から昭和にかけて、京都市立絵画専門学校の指導者として多くの後進を育て、日本画の近代化を牽引した。
その栖鳳が1942年に制作した《海幸》は、彼の最晩年に位置する。すでに病床に伏すことの多かった時期にあっても、栖鳳は筆をとり、日本画における伝統的な画題を、近代的な眼差しで再解釈しようとした。そこには、芸術家としての最終的な自己確認と同時に、時代から求められる「国民的表象」との妥協の両方が潜んでいる。
神話的題材――海幸彦の寓意
「海幸彦・山幸彦」の物語は、『古事記』『日本書紀』に記される古代神話である。兄の海幸彦は漁具を、弟の山幸彦は狩具を交換して狩猟に挑むが、山幸彦は釣り針を失い、兄に責められる。山幸彦は海神の宮を訪ね、そこで海神の娘と結ばれ、失った釣り針を取り戻して兄を服従させるという筋立ては、自然の恵みと人間の営みの関係を象徴する。栖鳳が1942年にこの題材を選んだことは偶然ではなく、日本が国体思想を強調し、神話的起源を国民に喧伝した時代状況を反映していると考えられる。
《海幸》には必ずしも物語全体が描かれているわけではなく、海の恵みを享受する情景、あるいは漁具や魚介の描写を中心とする解釈も可能だろう。しかし「海幸」という題名自体が、古代神話への連想を避け得ない。栖鳳は伝統的な画題を通じて、国家的イデオロギーと自らの芸術を結びつけるという、きわめて微妙な課題に取り組んでいたのである。
技法と構図――写実と装飾の均衡
竹内栖鳳の画技の核心は、写生に基づく精緻な観察と、それを装飾的に再構成する構図力にあった。《海幸》においても、魚や海の生物は写実的に描かれつつ、画面全体は装飾的なリズムで統合されている。例えば魚の鱗や甲殻の輝きは、細やかな筆致で一枚一枚描き分けられており、生命感があふれている。同時に、それらは画面の対角線や曲線に沿って配置され、観者の視線を導く意匠的構成が施されている。
また、絹本彩色という素材が作品に独特の透明感を与えている。絹地の上に重ねられた絵具の層は、光を透過し、奥行きのある輝きを放つ。海の青や魚の赤は、ただの色彩ではなく、素材の特性を活かした光の現象として表出する。栖鳳は日本画材の特性を熟知し、それを最大限に引き出すことで、伝統と革新を同居させることに成功している。
戦時下の文化的文脈
1942年という制作年を考慮すると、《海幸》は戦時下文化の一断面として理解する必要がある。紀元2600年記念事業以来、神話的題材は国家的シンボルとして再評価され、美術もその枠組みの中で利用された。竹内栖鳳は決して戦意高揚を直接的に描いたわけではないが、「海幸」という題材を選んだ時点で、神話的国民性の強調と無縁ではあり得なかった。だが同時に、彼はあくまで画家として対象を観察し、筆致の精緻さや色彩の豊かさを追求した。そこに、芸術家としての誇りと、時代の制約をどう折り合わせるかという葛藤が見てとれる。
興味深いのは、同じ1940年代に横山大観や川合玉堂らが描いた作品と比較したとき、《海幸》がより対象の具体性を重視している点である。大観の水墨画が国家的精神性を象徴する抽象的イメージへと傾いたのに対し、栖鳳の筆は、魚の質感や水の輝きといった具象的ディテールにこだわり続ける。これは栖鳳の画業全体に通じる「写生第一」の信念であり、彼が最後まで貫いた芸術的矜持であった。
日本画史における位置づけ
《海幸》は竹内栖鳳の最後期に属する作品として、日本画史上特別な意味をもつ。明治期に始まった日本画の近代化運動は、大正・昭和を経て、国際的潮流と国家的要請のはざまで揺れ動いた。栖鳳はその中心で常に革新を試みながら、最終的には伝統的素材と神話的題材に回帰した。それは退歩ではなく、むしろ円熟の到達点であったといえる。
《海幸》はまた、戦時下の国家的要求に応じながらも、対象の生命を尊重する写生精神を失わなかった点で、栖鳳の芸術観の精華を示す。彼にとって絵画は、国家に奉仕する道具である以前に、生き物の命を捉え、それを美として昇華する行為であった。その矛盾と緊張の中にこそ、この作品の真価がある。
結語――最晩年の筆に宿るもの
竹内栖鳳《海幸》は、単なる神話的主題画でも、戦時下のプロパガンダ作品でもない。それはむしろ、栖鳳が生涯追い求めた「生の写し」と「装飾的統合」とを、神話的題材のなかに結晶させた一点である。海の恵みを描きながら、そこに宿る生命力の煌めきを捉えることに成功したこの作品は、画家の死の年に制作されたことも相まって、遺作的な意味を帯びる。そこには、自然へのまなざしと芸術への信念を最後まで貫いた巨匠の姿が映し出されている。
戦時という時代の重圧のなかでなお、対象を見つめ、生命の輝きを描き出した竹内栖鳳の筆。その結晶としての《海幸》は、近代日本画の複雑な歴史を体現し、今日に至るまで静かに、しかし力強く語りかけている。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)




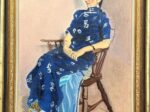

この記事へのコメントはありません。