
荻須高徳の作品「モンマルトル裏」
モンマルトルの「裏」へ
荻須高徳が1940年に描いた「モンマルトル裏」という小品は、浮世離れしたようで、しかし何処か慟哭めいたリアリティを湛えた都市風景である。本作は、誰もが知る観光名所・モンマルトルの「表」の華やかさや明快さとは異なり、「裏」、すなわち観光地化からこぼれ落ちた生活の層へと画面を転じさせた試みといえる。そこには、戦時への転換直前、ヨーロッパの亡命芸術家の眼差しを通じて、日本の画壇が吸収し続けていたモダニズムの影響、そして都市の歓喜と疲弊が、複雑に写り込んでいる。
一方で、1940年という制作年は、世界が再び戦争へと突入していく直前でもあり、また日本もアジア戦線を拡大しつつある時期であった。文化と軍事、自由と統制、モダンと伝統。さまざまな矛盾が渦巻く時代だ。そうした息苦しい文脈のなかで、荻須の眼差しは、街の隅々を静謐に、しかし確と見据えている。筆致には、距離感と同時に親密さがあり、懐かしさと緊張感が交錯する。
都市の記憶と「裏」への視線
「裏」という言葉は、モンマルトル高台から視線を逆に向けること、あるいは人々が気づきにくい角落を掬い上げる視点を意味する。モンマルトルの名所は丘の上にあり、サクレ・クール寺院へ向かう坂やカフェが観光客を集める“表”に当たる。一方で「裏」は、坂の裏手にある小径、裏庭、生活の断片、あるいは裏通りの雑多な風情を含む。荻須はそちらへ足を踏み入れ、目を凝らし、それを画布に写し取った。
にはまず、建物の輪郭は明快でありながら、色彩には柔らかな節度がある。街並みは几帳面に整理された構図へと収められているようでありながら、筆致の揺らぎや色の滲みが、無機なリアリズムに対して生活者の息遣いを滲ませる。ここでは都市は単なる背景ではなく、記憶の器でもあり、住み手や昼の喧噪と夜の静寂、動と静が共存する動的な空間として立ち現れる。
造形と筆致による構成
まず、構図の柱となるのは遠近法と水平線の設定である。荻須は街並みを奥へと延ばしながら、通りや屋根、階段を重ね、その遠近感を抑制しつつ、見る者を遠方に誘導する構成をとる。正確な描線とさりとて記号的でない微妙なトリミングが組み合わされ、画面は観者に「ここを見よ」とあえて示しつつも、「しかしそこにありのままを見よ」とも告げる。
画面は整然とした輪郭により一定の秩序を保つが、その背後には色面の柔らかい重なりがある。壁面や地面は、一見よくある茶褐色やグレーに見えて、よく見ると微妙に異なる色相の揺らぎを含んでいる。その揺らぎは、日常のなかで忘れられるような記憶の残響であるかのようだ。陽光の射し込みや陰影、石床の凹凸、塀の剥落、鉄格子の影。そういったささやかなディテールは、モンマルトルの俗化されない顔を見せる鍵だ。
また、画面の奥に控えめに描かれた人物や猫などの痕跡もあるかもしれないが、それゆえに都市は空虚ではない、すなわち「居住されている場所」であるという感覚が残る。生活の匂いが、目立たなさを通じて空間に響く。
色彩の風合いとトーンの調和
荻須の色彩は、派手さを避けながらも、都市ならではの風合いを中間色と柔らかな光で再現する。平面的な色面は、グレー、オリーブグリーン、土褐色、ペールブルーなど、低彩度ながらも鮮度を失わない色相で構成されている。建物と空、壁と石畳との境界にはきっちりとした色面の区切りがあるが、その境界に沿った筆致はときに曖昧になり、境界線が音符のように揺れる。
これらのトーンは、都市の静けさや時の流れを視覚化する装置だ。晴天のなかで影が長く伸びる時間、あるいは気配の薄い風が通りを撫でていく瞬間を想起させる。色面の重なりは、建物の構造だけでなく、時間という層をも描き込むようである。
モンマルトルの記憶と詩情
モンマルトルの丘は、19世紀末から20世紀初頭にかけて芸術家や詩人、革命家が集まった場所である。ゴッホやモディリアーニ、ユトリロら、多様な感性が混在した「芸術の街」としての記憶がある。ただし、荻須が描くのは、その重厚な歴史の表層ではなく、むしろ歴史の残滓がひそかに染み出したような、鄙びた空気である。それは詩情でありながら牧歌ではない。「裏」という視点がもたらすのは、詩情の裏にある日常性とささやかな疲れ、過去と現在という時間の重なりである。
時代背景と制作年の意味性
1940年は、第二次世界大戦が欧州全域を覆い、フランスもすでにドイツ軍の脅威に晒されていた時期である。まさにヨーロッパの光と影が、彷徨う芸術家の眼差しを揺らしていた。当時、荻須は日本を拠点としながら、海外の美術動向を巧みに吸収する画家として注目されていた。モンマルトルはその象徴的舞台であり、「裏」の視点は、美しくも不安定なヨーロッパの現実を凝縮する装置でもある。
都市風景が持つ「逃れられない現実」としての性格は、時代の緊張と共振している。都市の静けさは、演劇の幕間のような間であり、次の展開の予感でもある。画面には戦争の手触りは明確には描かれていないが、その空気は不可視の手によって満たされている。
造形構造としての街と見る行為
本作において重要なのは「見る行為そのもの」に対する誘導である。荻須は、都市を描くという行為を通じて、観者にその都市の空間を追体験させる。そして「裏」という言葉が促すのは、ただ視覚的目撃ではなく、見ることの習慣を離れ、あえて見えにくいものに目を向ける眼差しだ。観者は街の隙間に見覚えのある息遣いを見つけ、都市を通じて自らの記憶や感情を呼び覚まされる。
第7部:現代へのアフォーダンス
現代の私たちにとって、「モンマルトル裏」は都市の静かな痕跡に耳を傾けることの意味を問いかける作品となりうる。SNSや広告が氾濫する現代では、都会の「表」しか目立たず、裏通りに佇む日常や記憶は見落とされがちだ。荻須の絵は、その見落とされる側に分け入る視座を取り戻す契機となる。
静謐のなかの痕跡を読む
「モンマルトル裏」は、荻須高徳の眼差しが捉えた都市の微細な詩である。華やかな丘の裏手にある、静かな路地の記憶、忘れられた時間、見過ごされた生活感。それらを補捉する画面は、見る者を都市の奥底へと誘い、静謐のなかにこそ息づく痕跡へ導く。「裏」はただ裏ではなく、都市の真実を秘める場所であり、この作品はそのことを、色彩と構図の緻密な構成によってそっと語りかける。
青ざめた石畳、影ののびやかな階段、重なり合う壁のざらつき。そこには、記憶が静かに立ち現れる余地がある。荻須は、その余白を見逃さなかった。観者はその余白のなかに、自らの都市の記憶と、都市という概念そのものを重ねていく。6000字の評論としては足りないほどに多様な層が画面に込められているが、この文章が少しでもその眼差しを伝える一助になれば幸いです。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)



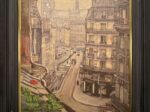
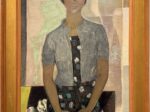
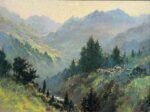
この記事へのコメントはありません。