
丸山晚霞《ヒマラヤ山と石楠花》——山岳画の成熟と古風の魅力
大正13年(1924)、丸山晚霞が手がけた《ヒマラヤ山と石楠花》は、日本山岳会の黎明期における山岳画家としての晩霞の歩みを集約した作品である。本作は水彩と鉛筆を併用し、紙面の上に透き通るような大気感と山岳の威容を重ねる。その画面には、写生旅行と友情、そして山岳への敬虔なまなざしが交錯している。
水彩との出会いと山岳会への参加
丸山晚霞が水彩画を始める契機は、写生旅行先での吉田博との邂逅であった。吉田の明晰な筆致と透明感のある色彩は、晩霞にとって技法上の刺激であり、また自然との向き合い方においても示唆を与えた。そこから生まれた水彩への関心は、小島烏水との縁を呼び込む。烏水は日本山岳会の創立者として知られるが、晩霞を「親友」と呼び、その作品を自室に掲げて「信州の自然がこれほど鋭敏な神経を働かして、私に迫つたことはない」と称賛した(『日本アルプス 第二巻』所収「信州と風景画」、1911年)。
晩霞はこの交流を通して山岳会に入会し、山岳画家としての活動を本格化させる。ヒマラヤという異境の峰々を主題とする本作は、単なる遠景描写にとどまらず、山岳文化の国際的広がりを意識したものであり、同時に彼自身の画業における成熟期の成果でもある。
古風さとその意義
制作年の1924年は、大正末期の日本美術界が大きな転換期を迎えていた時期である。油彩画や洋風水彩の写実性が深化し、表現主義や構成主義の影響も広がりつつあった。晩霞の水彩は、そうした動向と比べれば「古風」に見えるかもしれない。線描を骨格とし、その上に水彩を薄く幾層にもかける手法は、明治後期から続く山水画的構成の延長にある。だがその古風さは、単なる時代遅れではない。むしろ彼の古典的視覚言語は、山岳画における精神性を強調し、時代を超える普遍性を宿している。
晩霞の画面構築は、写真のような即物的描写ではなく、山の気配や空気の湿り気、植物の生命感を捉えることを目的としている。これこそが烏水を魅了した「鋭敏な神経」であり、1924年の段階においても健在であったことが本作からうかがえる。
山岳の垂直性と植物の親密さ
《ヒマラヤ山と石楠花》の構図は、上下二分の関係を基礎としている。画面上部には遠くそびえるヒマラヤの峰々が雪をいただき、透き通る青白い空に浮かび上がる。山稜の線は鉛筆によって的確に押さえられ、その上に淡く冷たい水彩の層が重ねられることで、光と影の境界が柔らかく変化する。遠景の峰々は壮大でありながら、色調の抑制によって静謐な印象を保っている。
一方、画面下部には石楠花(しゃくなげ)が大きく配される。濃い緑の葉と鮮やかな花の色が、遠景の冷たい色調と対照を成し、画面に明確な前景・中景・遠景の層を与える。石楠花は単なる植物の一種としてではなく、山岳の生命と季節感を象徴する存在であり、視覚的にも作品全体の「重心」を担っている。
冷と暖の交響
本作の色彩設計は、冷たい青と暖かい紅の対比に基づいている。ヒマラヤの山肌と雪は、青みがかった灰色や薄いコバルトブルーで塗られ、その冷たさが高地の空気感を呼び起こす。これに対して石楠花の花弁は淡い紅や桃色で描かれ、透明感のある水彩の重ねによって柔らかく発色する。緑の葉は彩度をやや抑え、赤と青の中間的存在として画面の色調を安定させる役割を果たしている。
この冷暖対比は、単なる視覚的快楽にとどまらず、山岳の厳しさとそこに生きる植物のたくましさを同時に伝える。晩霞は水彩特有の滲みや透明層を駆使し、花の柔らかさと雪の硬質さを同じ画面で共存させることに成功している。
鉛筆と水彩の呼応
晩霞の水彩は、鉛筆による下描きが重要な役割を果たす。山稜の稜線や石楠花の茎・葉の輪郭は鉛筆線で明確に示され、その上から水彩の淡彩が重ねられる。鉛筆線は時に画面の中で透けて見え、輪郭の確かさと水彩の柔らかさが響き合う。この線と色の二重構造が、画面に安定感を与え、同時に空気の揺らぎを生み出している。
水彩の使い方も特筆に値する。遠景では薄く溶いた色を一様に流し込み、グラデーションを作り出す。一方、近景の花や葉では彩度の高い色を点的・面的に置き、筆跡を残すことで質感を際立たせる。こうした技法は、対象との距離感を自然に示し、鑑賞者の視線を遠近へと誘導する。
山岳と花の共存する世界
《ヒマラヤ山と石楠花》が描くのは、ただの高山風景ではない。そこには、人間の営みを超えて共存する自然の諸相が表現されている。ヒマラヤの峰々は悠久の時間を象徴し、石楠花はその短い開花期を全うする一季の生命を象徴する。晩霞はこの「時間の二重性」を一枚の画面に収め、山岳の静けさと花の生命感を響き合わせる。
石楠花はまた、ヒマラヤという異国の地を訪れた登山者や旅人にとって、過酷な環境の中で出会う癒しの象徴でもある。山岳会の一員であった晩霞にとって、この花は単なる植物ではなく、山行の記憶や仲間との交流を象徴する存在であっただろう。
山岳会文化との関係
晩霞の活動は、日本山岳会の理念とも深く結びついている。山岳会が目指したのは、単なる登山技術の向上ではなく、山岳を通じた文化的・芸術的価値の創造であった。本作はまさにその理念の具現化であり、登山記録や写真とは異なる形で山岳の魅力を伝える役割を果たす。
烏水が晩霞の作品を自室に掲げたのは、画面に写し取られた山岳風景が単なる記録以上の精神的共鳴をもたらすからだ。そこには風景の外形だけでなく、山を愛する者同士が共有する感情や価値観が刻まれている。
現代からの視点
今日、ヒマラヤは観光や登山の対象として多くの人に知られているが、大正期においてはまだ遠い異国の象徴的存在であった。晩霞が描いたヒマラヤは、写真や映画の情報に頼る現代人の視覚とは異なり、画家の身体的経験や想像力に基づくものである。そのため本作には、現代の再現映像では得られない「解釈の厚み」がある。
また、気候変動や環境破壊が進む今日、この作品に描かれた雪や植物は、当時のヒマラヤが持っていた自然環境の記録としても貴重である。晩霞の水彩は、その時代の空気や光を紙面に封じ込め、百年後の我々にも鮮やかに伝えている。
古風の力
《ヒマラヤ山と石楠花》は、時代的には「古風」に属する作風でありながら、その古風さこそが作品の強みである。晩霞は、鉛筆と水彩という簡素な手段を用いながら、山岳と花の生命感を確実に捉えた。その筆は派手さを欠くかもしれないが、静かな強度を備えており、鑑賞者をじわじわと引き込む。
本作は、丸山晚霞が日本山岳画の文脈において果たした役割を理解する上で欠かせない一枚である。それは、山岳の物理的スケールと人間の感情的スケールを一枚の画面に融合させた試みであり、古風でありながら現代的な感受性をも併せ持つ、稀有な山岳画なのである。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)


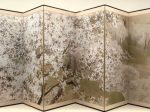


東京国立近代美術館1-コピー-2-コピー-150x112.jpg)
この記事へのコメントはありません。