
恋の視線と背景の交錯
河野通勢が描いた《好子像》は、1916年(大正5年)という時代に生まれた一風変わった人物画である。タイトルにある「好子」とは、通勢が想いを寄せた女性だとされ、その描写には鑑賞者にも知られざる思いの温度が満ちている。モデルが手にしているのは、アルチュール・ジョネ『芸術の起源』という書物。それにぶどうの実と若葉を添えることで、知識と自然、そして豊穣や生命の象徴性が重なる複雑なモティーフとなっている。そして、首にかけられたペンダントには「画家のイニシャル」が刻まれ、無言の主張を画面に投じる。背景には故郷・長野の園景が広がり、汽車の白煙、画架に向かう画家の姿、ぶどう棚への散水をする男性など、日常と非日常、想いと現実がひとつの構成空間に交差する。
通勢は、美術教師であり写真館を経営した父・河野次郎のもとで育ち、父が取り寄せた洋画集から西洋古典絵画に親しみ、知性の源泉として吸収していた。そうした素地があるからこそ、《好子像》は単なる肖像にとどまらず、恋という感情と芸術、そして記憶と風景が同時に描かれる複層的なものとなっている。
制作の土壌――長野時代と画家の眼差し
通勢が長野にいた頃の制作である《好子像》は、例えば汽車の煙や庭の手入れといった小さな日常が、彼にとって風景と感情を重ね合わせる装置だったことがうかがえる。古典絵画を知っていた背景を取り込み、「モナリザを思わせる女性像」に転倒させる大胆な比喩は、西洋への憧憬と日本的な繊細な叙情が同居している。
また、当時の日本における肖像画の規範は、写実や清潔感に寄せられる傾向があったが、通勢はそうした枠に安住せず、感情と芸術の象徴を多層的に構築しようとした。この構造は、絵画内に「現実(長野の風景)」と「想像(恋/モナリザ)」を同居させることによって成り立っており、受容者の視線を自然と、また感覚的に引き込む複雑さを孕んでいる。
構図――視線の導きと細部の大洪水
絵画の構図は、まず前景の好子に視線が吸い寄せられ、その細部にあるペンダントや持ち物、手の位置に目が留まり、その後に背景の風景へと広がっていく構造となっている。モデルの視線は遠景を見据えるようであり、それは鑑賞者と画中の男性との間の視線のズレを感じさせ、見る者自身を物語の当事者として引き込む作用を持つ。
画面の奥には、ぶどう棚があり、そこに手入れをする男性が見え、《芸術の起源》の本、モデルの周囲にある自然の要素など、それぞれが丹念に描き込まれている。樹々の葉やぶどうの果実、布の襞までも精確に描写されており、ディテールの「洪水」が画面全体に密度をもたらしている。この意識的な描写は、通勢自身の写真に基づく観察眼が手元にあることを暗示するとともに、一方で「写し」と「描く」のあいだの境界を濃密に揺らがせる。
対比と調和――古典的フォルムと近代的空間
モデルを「モナリザ」に見立てる手法は、古典絵画の神秘と微笑を通勢なりに翻案する試みだ。その神秘的な微笑や穏やかな微妙さは、好子の表情に秘められているかもしれない。けれども、《好子像》における微笑はむしろ感情を明示せず、遠くを見つめることで存在する静的な力として閉じ込められている。
対して、背景を占める動的な要素――汽車の煙、人物の運動、庭の手入れする様子――は、静謐な前景と緊張感を生みながら調和する。古典を模すフォルムと、近代都市の匂いを帯びた要素が、ひとつの画面内で屈折し、1916年当時の日本画壇における過渡期的感覚を象徴する。
象徴性――ペンダントと書物とぶどう、記号の重層
モデルの手にある『芸術の起源』という書物は、芸術に対する通勢の自覚的な姿勢を表している。ボタン一つじゃなく、ぶどうの実と若葉を抱えることで、豊饒や成長生命、自然との融和といった象徴との接点が設けられている。さらに、首にかけられたイニシャル入りペンダントは、恋の自意識と画家の存在(自己と他者の交差)を仄かに告げる。
こうした記号の重層は、好子が単なるモデルではなく、通勢の中で結晶化した一人の象徴的女性として描かれていることを示す。それは、絵画が描く対象を超えて、芸術という媒介を通して成立した記憶と感情の構造である。
表現技法と精密描写の対位法
画面全体に渡る精密な描写は、通勢が写真を理解し、技法の一部として採り入れていたことと無関係ではない。細密な描写は、観察者には幸福なリアリティをもたらすが、そのあまりの詳細さが逆に幻想的な深みを与えることもある。本作において葉や果実、布の皺などの細部は、思わず触れたくなるほどの質感に満たされ、同時にそれが全体の構成を陶酔的な調和で束ねている。
これにより、絵画の「見る喜び」が二重に押し寄せる。ひとつは描写の再現性による安心と即時性。もうひとつは細部の積層が心理的空間を呼び起こす詩的余韻を産むという構造だ。
時代文脈と画派的位置づけ
1916年という時点の日本では、西洋画の受容と翻案が盛んで、特に洋画教育を受けた画家たちは、写実と感情律のバランスを模索していた。通勢はその中にありつつ、人物像に恋愛的な投影を加えるという私的な方向を選んだ。その私事としての表現性は、同時代の公共的な美術の流れにおいても異彩を放つ。
また、写真館という家庭環境は、通勢に“写真的写し”と“画家的転写”を行き来させる実験場だったと想像できる。“思い出”という時間の層を絵画に定着させる試みは、そのような視覚と記憶の混在の中で熟成されたものだろう。
鑑賞とその余白
鑑賞者はまず、モデルの静謐な視線に引き込まれる。だが、視線は画面外へと逃げており、見る者はどこに視線を置くべきか、あるいはどこまで入ってよいのかを問いかけられる。その後、背景の細部に目を転じると、そこには小さな物語が重層的に描き込まれており、見るほどに時間が巻き戻され、過去の情景や感情に心が浸透してゆく。
この構造は、鑑賞者自身にこの絵画を「解く」よりも「体験する」よう促す。つまり、目線は遠くへ、意識は感情と記憶の源へと自然に流れていくのだ。
モナリザの影を伴った園庭の詩
《好子像》は、通勢が恋と美、記憶と風景を画面に穿つことで成立した異色の肖像画である。古典への憧れと故郷への眼差し、そして内なる感情の吐露。それらが混じり合い、画面はときにミステリアスに、あるいは甘い郷愁を帯びて、今も静かに鑑賞者に語りかける。
恋した相手をモナリザに見立てる大胆さと、それを日常風景の中に定置する細密さ。静寂と装飾性のはざまに立つこの肖像は、単なる人物画以上の詩性と時を包む力を備えている。そして長野の園、汽車の白煙、そして画家の視線の行方は、通勢の世界を今も内包し続けている。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)





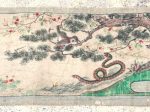
この記事へのコメントはありません。