
速水御舟の作品《京の家・奈良の家》
1920年代、日本画は伝統と革新のはざまで大きく揺れ動いていた。京都画壇の保守的な体制や東京の再興日本美術院による新風など、画家たちは多様な美意識と理想のなかで自らの進路を模索していた。そんな時代にあって、速水御舟(1894–1935)はきわめてユニークな位置を占める存在である。その生涯はわずか40年あまりと短いものであったが、彼の制作は質・量ともに密度が高く、その実験的精神と美術への真摯な姿勢は、近代日本画の中でも際立っている。
《京の家・奈良の家》(1927年制作、)は、御舟の円熟期にあたる作品であり、その題名の通り、京都と奈良という日本文化の根幹をなす古都の風景、あるいは家屋に焦点を当てた連作的な構成を持つ。紙本彩色によって描かれた本作は、見た目の静謐さの裏に、極めて綿密な観察と意識的な構成が潜んでおり、単なる風景画や記録画には収まらない深層を抱えている。御舟にとって「家」とは、空間であると同時に時間であり、ひとつの「場」に凝縮された文化的記憶そのものであった。
まず、《京の家・奈良の家》に接するとき、我々が最初に感受するのはその静けさである。だがそれは、単なる無音や無為の静けさではない。むしろ、あらゆる喧騒をそぎ落とした果てに現れる「沈黙の構築」とでも呼ぶべき緊張感をたたえている。

画面は、簡素かつ端正な構図によって構成される。いずれも木造の家屋をモチーフとしており、京の家は洗練と秩序を感じさせる町家風の正面、奈良の家はどこか素朴で古雅な、民家的風情の残る建築が描かれている。御舟はこれらを真正面から捉えるのではなく、わずかに斜めから、あるいは周囲の自然環境との関係性のなかで描くことにより、建築が単なるモチーフ以上の存在であることを提示している。
特筆すべきは、透視図法的な遠近ではなく、日本画特有の平面的な視覚構成が活きている点である。たとえば、屋根瓦の連なりや格子の繰り返し、板壁の風合いなどが、細密に、かつフラットな描写で積み上げられる。それらは単なる装飾ではなく、空間を切り取る「枠組み」として機能しており、観る者の目を外へと流出させるのではなく、画面の内側へと、より深く沈潜させる。
速水御舟の絵画において、素材そのものの性質に対する鋭い感性は常に注目されてきた。《炎舞》における炎のきらめき、《名樹散椿》における花弁の質感表現などに見られるように、御舟は視覚的印象を超えた「触覚的リアリズム」を追求していた。そして《京の家・奈良の家》でも、この素材へのまなざしは存分に発揮されている。
特に目を引くのは、木材の描写である。柱や梁、格子や建具などに用いられる木は、それぞれ異なる質感と経年変化を湛えており、御舟はその微細な差異を見逃さない。節の入り方、表面の割れ、日焼けによる褪色、雨風による風化——それらを彩色と線描の精緻なコントロールによって再現している。
また、家屋に差し込む光と影の表現も印象的だ。朝や夕の斜光線が、格子の隙間から柔らかく入り込むさま、庇の影が壁面に落とす繊細な陰翳。それらはすべて、光が物質に触れたときに生まれる詩的な瞬間を捉えている。そしてその舞台として選ばれたのが、木と紙という伝統的な日本家屋の素材なのだ。御舟の筆は、木を木として、紙を紙として描くことによって、それらが織りなす「日本の時間」を表現している。
《京の家・奈良の家》は、単なる建築物の写生ではなく、歴史と文化の厚みをもった「場」の記憶を描いている。京都と奈良という二つの都市は、日本の古代から中世、そして近代に至るまで、連続的かつ断絶的に文化の中心であり続けた。その都市空間には、無数の人々の営みと、時の堆積が刻み込まれている。
御舟は、そうした「記憶としての都市風景」を、あくまでも静謐な様式で描き出す。彼は観光的な視線を排し、視覚的なインパクトを避ける。たとえば有名寺社の華やかさや、桜や紅葉といった季節の演出すら存在しない。そのかわりに、彼が選ぶのは、何気ない一軒の家、あるいは路地裏の片隅である。
その選択には、都市の表象を通して歴史を語るという、御舟の美術観が示されている。彼にとって都市とは、物語の舞台であると同時に、その物語が失われつつある「現在」において、最後の痕跡をとどめる場所なのだ。御舟の絵は、その喪失を予感しながらも、記録として描くのではなく、「感覚としての記憶」を再構築しようとする。
御舟の画業全体に通底するのは、常に「様式の越境」である。初期の院展的写実を経て、《炎舞》《夜桜》《名樹散椿》といった象徴性の高い作品へ、さらに晩年には極端に抽象的な水墨画まで手がけている。その変遷は一見バラバラに見えるが、どの時期も「観るとは何か」「描くとは何か」という問いへの実験であった。
本作《京の家・奈良の家》は、そのような実験の中でも、具象と抽象の均衡を取る稀有な例である。家屋は写実的に描かれているが、それは写真のような客観的写実ではない。むしろ、装飾的な線のリズムや構成的なバランスが、どこか抽象絵画のような感触をもたらす。
1927年にこの作品が描かれた当時、御舟はすでに新しい日本画のあり方を模索していた。だがその努力は、彼の健康と引き換えであった。結核により病床に伏す日も多くなっていた彼にとって、風景や静物の描写は、どこか死の予感と裏腹であったかもしれない。
《京の家・奈良の家》に漂う寂しさ、過度な演出を避けた沈黙のトーンは、そのような画家の内面とも響き合っている。どこか人の気配のない風景、時間が止まったかのような建物。だがそれは死の象徴ではない。むしろ、静かに生きているもの、時のなかで少しずつ風化してもなお在り続けるものの美しさを、御舟は肯定的に描き出している。
家屋という存在は、画家自身がいずれ去りゆく「この世界」の象徴であり、同時にそこに残される何か——形あるものの中に潜む無形の気配——を記録する手段でもあった。その意味で、この作品は「最後の風景画」であると同時に、「記録されざるもの」への鎮魂である。
《京の家・奈良の家》は、単に美しい日本家屋を描いた作品ではない。それは、風景が歴史であり、素材が記憶であり、構図が哲学であるということを、静かに語りかけてくる作品である。速水御舟は、日本画という形式の限界を広げることに成功したが、それ以上に、絵画というメディアを通して「時と場と人」の本質に迫ろうとした稀有な芸術家であった。
その試みは、今日の私たちにとってもなお新しく、なお鋭い。何気ない家の風景のなかに潜む無数の記憶とまなざしに、我々は再び、絵画の力を見出すことができるだろう。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)

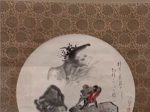




この記事へのコメントはありません。