
パブロ・ピカソ,国立西洋美術館,版画,展覧会「ピカソの人物画」
会場:国立西洋美術館
会期:2025年6月28日[土]-10月5日[日]
「青い胴着の女」
──古典と革新のはざまで揺れるピカソの1920年代
ピカソ、静かな転回の時代
パブロ・ピカソ(1881–1973年)という名は、20世紀美術の代名詞として世界中に知られている。キュビスムの創始、シュルレアリスムへの接近、陶芸や舞台美術への挑戦など、彼の創作は常に革新を追い求め、時に時代の感性を先取りしながら、膨大な作品群を遺した。しかしその長い創作人生のなかでも、1920年代前後の数年間は特異な光を放っている。ピカソがあえて「古典」に立ち返ったこの時期は、革新の中の静けさと、均衡への希求が共存する、いわば「間奏曲(インテルメッツォ)」のような時代だった。
そのような1920年に制作されたのが、《青い胴着の女》である。この作品は、鉛筆、水彩、グアッシュという比較的軽やかな素材を用い、紙に描かれた中型サイズの作品であるが、その中にはピカソの古典主義的な要素と、現代的な感性とがせめぎ合う豊かな緊張が潜んでいる。
現在は国立西洋美術館の松方コレクションとして収蔵されており、日本でも広く紹介されているこの作品について、以下ではその歴史的文脈、造形的特徴、そしてピカソの芸術観との関係性に触れながら、その魅力を一般読者向けに読み解いていく。
《青い胴着の女》が描かれた1920年は、第一次世界大戦終結からわずか2年後のことである。大戦後のヨーロッパは、精神的にも文化的にも大きな衝撃を受けていた。人々は近代の急激な進歩とその破壊的帰結に疲弊し、混沌から秩序への回帰を求めていた。それは芸術の世界においても同様で、激しい抽象表現や実験的様式から一転、静謐で調和的な表現への憧れが生まれていた。
ピカソもまた、その流れの中にいた。彼は1910年代において、キュビスムの先駆者として絵画表現を根本から覆すような革新を行ってきたが、戦後の数年間は、より具象的で静かな表現へと方向転換していた。いわゆる「新古典主義」の時代である。
この時期、ピカソはイタリア旅行で古代彫刻やルネサンス絵画に触れ、その造形的均衡や人物像の落ち着いた重みから深い影響を受けたとされている。《青い胴着の女》も、そうした古典への共鳴の中で生まれた作品のひとつであり、柔らかな光と簡潔なフォルムによって、まるで古代彫像のような静かな気品を漂わせている。
作品のタイトルにある「青い胴着(どうぎ)」とは、上半身を覆う衣服の一種であり、しばしば中世風のコスチュームや演劇的な衣装を想起させる。この青い胴着を身にまとった女性像は、現実の誰かをモデルにしているというよりは、ある理想的な女性像、あるいは精神的な「女性性」の象徴として描かれているように見える。
ピカソが用いた青の色調は、決して鮮やかなものではない。むしろ少し褪せた、灰青色に近いトーンで、深い落ち着きと内省を感じさせる。この青は、かつての「青の時代」(1901〜1904年)に見られた悲哀の青とは異なる、より成熟した色彩である。
衣服の表現においても、装飾性よりも形態のシンプルさが優先されている。袖の落ち感や布のたるみが丁寧に描かれており、衣服を通して身体の輪郭や姿勢が静かに浮かび上がる。衣服は単なる装いではなく、身体性や存在感を伝えるための重要な造形要素となっているのだ。
《青い胴着の女》における女性の表情は、きわめて控えめである。視線はやや下を向き、口元には感情の起伏がほとんど感じられない。笑ってもいなければ、悲しんでもいない。無表情というよりも、感情を静かに内に湛えた「沈黙」の表情である。
このような表情は、古代ギリシャ彫刻やルネサンス期のマドンナ像に通じるものであり、普遍的な美のかたちを追求しようとするピカソの姿勢がにじみ出ている。観る者に何かを強く訴えるのではなく、むしろ「見られること」に静かに耐えるような、受動性をたたえた姿勢は、20世紀初頭の肖像画においてきわめて稀有な存在感を放っている。
また、手の表現も重要である。女性は手を静かに胸元に置いており、そのしぐさは内省や自制を象徴するかのようだ。力強く自己主張するのではなく、自らの存在を淡く保ちながら、その内面に確かな重みを感じさせる。ピカソの線はこの手の形を何度もなぞったかのように見え、そこに彼の意識の集中が感じられる。
《青い胴着の女》は、キャンバスに油彩で描かれた作品ではない。鉛筆による輪郭線と、水彩、グアッシュによる彩色という軽快な技法で描かれている。紙という支持体も相まって、作品全体には親密さと詩的な雰囲気が漂っている。
鉛筆の線は、ピカソらしい即興的で鋭いものではなく、むしろ柔らかく慎重な印象を与える。水彩とグアッシュは、布地の質感や肌のトーンを微妙に描き分け、光と影のあいだに繊細な層を築いている。
この技法の選択は、ピカソが油彩画の重厚さから距離を取り、より内面的で個人的な表現を志向していたことを示唆している。紙上に描かれたこの作品は、あたかも日記の一頁のように、ピカソの静かな思索の痕跡を留めている。
現在、《青い胴着の女》は東京・上野の国立西洋美術館に収蔵されている。これは、いわゆる「松方コレクション」と呼ばれる一連の西洋絵画の中の一作であり、日本の近代美術史においても特別な位置を占める。
松方幸次郎(1865–1950)は、戦前日本の実業家であり、第一次世界大戦中から戦後にかけてフランスで多数の西洋絵画を収集した。その眼は確かで、モネ、ゴッホ、ルノワールと並んで、ピカソ作品も早くからコレクションに加えていた。
当時の日本においてピカソはまだ広く知られていたわけではなく、松方の先見の明は特筆に値する。戦後、松方コレクションの一部が日本政府に寄贈され、1959年に国立西洋美術館の開館とともに公開されたことで、日本の観衆もようやくピカソを「実物」で体験できるようになったのである。
《青い胴着の女》は、派手さや劇的な物語性に乏しいかもしれない。しかしこの作品は、だからこそ強い。静けさの中にひそむ美、均衡のなかに宿る情感、そして即興と熟考のせめぎ合い。そのすべてが、一枚の紙の上に凝縮されている。
ピカソがこの作品を通じて示したのは、単なる古典主義への回帰ではない。むしろ、過去の造形語法をいったん受け入れたうえで、そこに現代の精神をどう吹き込むかという、彼の創造的実験のひとつの答えだった。
のちにピカソは、再び大胆な変革の道を歩んでいく。しかしその歩みは、こうした静謐な時代を経てこそ可能になったものだった。《青い胴着の女》は、ピカソ芸術の静かなる「呼吸」であり、その息づかいは100年後の今も、私たちに新たなまなざしを呼び起こしてくれる。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)





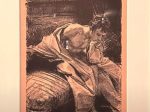
この記事へのコメントはありません。