【色絵姫形小皿】伊万里焼ーメトロポリタン美術館所蔵

色絵姫形小皿
平安への憧憬をかたちにする古伊万里の美
古伊万里の色絵磁器は、日本の工芸史において特別な輝きを放つ存在である。その成熟が見られる18世紀中頃、有田の窯場で生まれた「色絵姫形小皿」は、単なる器物の枠を超え、江戸の人々が抱いた“理想の過去”への憧れを端正な造形に託した希少な作品である。八つ折れ風の輪郭をもつ長方形の小皿は、正面から見ると一人の宮廷女性──黒髪を垂らし、重ねの衣に身を包んだ“姫”──の姿をかたどっており、形そのものがひとつの物語世界として立ち現れる。
本作の背景には、江戸時代中期の文化的潮流がある。町人文化が花開く一方で、宮廷文化への憧憬は強く残り、絵巻や物語絵を通して平安の女性像は理想の教養と美を象徴する存在として受容されていた。『源氏物語』や『枕草子』に描き出される優雅な世界は、江戸の人々にとって「古き良き日本」の象徴であり、そこに生きる女性たちは、洗練された美意識と知的な気品の結晶のように捉えられていた。
姫形小皿が象るその女性像は、写実的な表現ではなく、むしろ象徴性を帯びた抽象化に特色がある。顔立ちは控えめで、髪は流線のように整えられ、衣装の重なりは色絵の華やかな筆致によって際立つ。赤・緑・黄・金を主体とした上絵は、染付の青と響き合い、十二単の質感や装束の格式を装飾的に昇華している。金彩の控えめな輝きは、器としての落ち着きと、祝儀的な華やかさの双方を兼ね備え、視覚的にも触覚的にも豊かな層を形づくる。
造形技法にも注目すべき点が多い。姫の輪郭に沿って縁を波立たせ、髪や衣の起伏を立体的に造り出すには、通常の成形ではなく、人物像を意識した精巧な手仕事が求められる。裏面に至るまで丁寧な仕上げが施されていることから、本作が日常使いの器以上の価値を持つ「特別な品」として制作されたことは明らかである。実際、同種の姫形皿が複数確認されていることから、当時、女児の誕生祝いや雛祭りなど、晴れの日の贈答品として求められた可能性が高い。平安の姫君は、子どもの健やかな成長や優雅さへの願いを象徴し、その姿をかたどった器は吉祥性を帯びた存在となった。
18世紀半ばという制作時期も重要である。輸出向け有田焼が全盛期を過ぎ、国内需要に応えるための高度な装飾磁器が増えた時期に当たり、消費者層には趣味性の高い町人や上層商家が含まれていた。彼らは、器を生活の中に取り入れることで文化的教養を示し、また遠い過去への憧れを日々の暮らしに呼び込む媒介として愛玩した。本作もまた、日常と理想の世界をつなぐ“象徴的な小宇宙”として機能したと考えられる。
今日、この姫形小皿はニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵されている。同館がこの作品を単なる工芸品としてではなく、日本文化史を語る重要な資料として扱っていることは、本作が内包する文化的深みを物語る。器の形に託された平安への憧れ、江戸の美意識、そして有田の職人たちの確かな技──それらすべてが調和し、ひとつの物語として国境を越えて伝えられているのである。
掌に収まる小皿でありながら、そこに凝縮された時代の感性は、現代の私たちにも静かに語りかけてくる。美を暮らしの中に宿すという日本文化の精神は、今なお変わらぬ息づかいをもってこの小さな器に生きている。

コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)

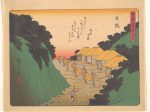




この記事へのコメントはありません。