- Home
- 07・江戸時代, 陶磁器
- 「岩花鳥図皿(がんかちょうずざら)(Dish with ,江戸時代,伊万里焼,岩花鳥図皿,rocks, flowers, and birds)」伊万里焼‐江戸時代ーメトロポリタン美術館所蔵
「岩花鳥図皿(がんかちょうずざら)(Dish with ,江戸時代,伊万里焼,岩花鳥図皿,rocks, flowers, and birds)」伊万里焼‐江戸時代ーメトロポリタン美術館所蔵

「岩花鳥図皿」― 江戸のやきものが語る、東西の美の交差点
鮮やかな色彩、緻密な文様、優美な構図。17世紀から18世紀初頭にかけて、九州・有田の地で生まれた「伊万里焼」は、海を越えてヨーロッパの王侯貴族を魅了しました。なかでも、メトロポリタン美術館に所蔵されている「岩花鳥図皿(がんかちょうずざら)」は、こうした美術工芸の東西交流を語る上で欠かせない重要な作品です。
本作は、1710年から1730年頃にかけて制作されたと考えられており、硬質磁器の素地に透明釉をかけ、その下に彩色の上絵を施す「色絵磁器(いろえじき)」として仕上げられています。直径19.4センチのこの小ぶりな皿には、岩、花、鳥といった自然のモチーフが豊かに描かれており、絵画や織物などの伝統的な東アジア美術の意匠をもとにしつつも、ヨーロッパ向けの嗜好が巧みに取り入れられています。
「伊万里焼」は、九州・佐賀県有田町周辺で生産された磁器を指す総称です。江戸時代初期、有田の泉山で磁器の原料である陶石(とうせき)が発見されたことを契機に、日本初の本格的な磁器生産が始まりました。磁器とは、きわめて高温で焼成された硬質の白い陶器で、釉薬の下に文様を描く「染付(そめつけ)」や、釉薬の上から絵付けを行う「色絵」など、さまざまな技法が発達していきます。
特に17世紀後半から18世紀初頭にかけて、伊万里焼はオランダ東インド会社(VOC)を通じて大量にヨーロッパへ輸出されました。この輸出用の磁器は、「オランダ伊万里」や「輸出伊万里」とも呼ばれ、色彩の豊かさや華やかさ、そして東洋的な神秘性から、各国の貴族や王室の人々を魅了しました。
「岩花鳥図皿」も、そうした輸出用伊万里の一例であり、日本の職人たちが外国の趣向に応えるかたちで生み出した芸術作品なのです。
岩・花・鳥という東洋の美
この皿の意匠の中心には、岩と木、そして水辺に佇む鳥の姿が描かれています。これは、中国絵画や工芸の世界でよく見られる伝統的なモチーフであり、「花鳥図(かちょうず)」として東アジアでは長らく愛されてきた構図です。
花鳥図とは、花と鳥を組み合わせて描いた装飾画の一種で、唐代以降の中国を中心に発展し、日本や朝鮮にも伝わりました。その根底には、自然との調和や四季の移ろい、あるいは吉祥の象徴といった思想が込められています。たとえば、牡丹は富貴を、松や竹は長寿や節操を意味し、鶴や雉(きじ)などの鳥は高潔や夫婦円満などの象徴とされてきました。
本作の皿に描かれた鳥は、その羽根の描写からすると鶺鴒(せきれい)や小鷺(こさぎ)などの水辺の鳥とも解釈できます。岩は力強い大地の象徴、木や草花は生命の繁栄や季節の美しさを表し、それらがひとつの絵画空間に調和して構成されています。
伊万里様式の密な装飾
「岩花鳥図皿」における装飾の密度と色彩の鮮やかさは、いわゆる「伊万里様式」の典型的な特徴です。この様式は、濃い赤や青、緑、金を基調とする華麗な色絵技法で知られています。
皿の中央部分に見られる鳥と岩のモチーフは比較的余白を生かした構図になっていますが、縁の部分には緻密な幾何学文様や花唐草(はなからくさ)、牡丹文などがびっしりと描かれ、視線を中央に向かわせるような効果を持っています。
こうした縁取りのデザインには、しばしば中国の明・清代の磁器、あるいはインド更紗や日本の染織文様の影響が見られます。さらに、文様を繰り返し配置するパターン装飾の技法は、東アジアの織物や金工、漆芸の装飾法にも通じるものがあり、異なる工芸の垣根を越えて発展した視覚文化の交差点とも言えるでしょう。
ヨーロッパにおける日本磁器の受容
18世紀初頭のヨーロッパにおいて、日本の磁器は「東洋の神秘」として熱狂的に受け入れられました。マイセンやセーヴルといった王立磁器工房が誕生する以前、ヨーロッパでは磁器の製造技術が未発達であったため、アジアから輸入される陶磁器は非常に高価で貴重な品とされていました。
伊万里焼は、その洗練されたデザインと技術の高さから、多くのヨーロッパの宮廷で重宝されました。とくにロココ時代の貴族たちは、日本の磁器を収集し、飾棚やキャビネットに並べて観賞しました。なかには、家具や建物の装飾として磁器を壁に埋め込むような例も見られ、「磁器の間(Porzellanzimmer)」と呼ばれる室内装飾文化が花開きます。
「岩花鳥図皿」もまた、こうした需要に応じて制作された品であり、絵画的な装飾と実用品としての実用性を兼ね備えた、まさに東洋と西洋の文化融合の結晶なのです。
描かれた“自然”と人間の想像力
「岩花鳥図皿」に描かれている自然の風景は、実際の風景を写したものではありません。むしろ、それは東洋美術における理想化された自然、つまり人間の内なる美意識によって構成された“心象風景”です。
東アジアの芸術において、自然とは単なる写実の対象ではなく、精神性や哲学と深く結びついた象徴世界でした。山は聖地を、川は循環を、鳥は自由や霊性を象徴します。この皿の絵柄も、そうした象徴的な意味を持ちながら、鑑賞者に静寂や清らかさ、あるいは自然との一体感を感じさせるように構成されています。
このような芸術観は、ヨーロッパの人々にとって新鮮であり、時に神秘的にすら映ったことでしょう。そこには、単なる装飾を超えた「自然へのまなざし」があり、それがこの皿をただの工芸品ではなく、「芸術作品」として成立させている大きな理由です。
時を超える器
およそ300年前、日本の職人の手によって焼き上げられたこの「岩花鳥図皿」は、いまやニューヨークのメトロポリタン美術館に収められ、世界中の人々に鑑賞されています。その歩みは、まさに一枚の小さな器がたどった「大きな旅」でした。
この作品は、日本のやきものが持つ高い芸術性と国際性を物語ると同時に、自然を愛で、四季を感じるという日本人の美意識をも体現しています。そしてまた、異なる文化を受け入れ、それを咀嚼し、独自のかたちで表現するという創造力の証でもあります。
「岩花鳥図皿」を見つめるとき、私たちは単なる装飾美以上のもの—すなわち、人類が自然とともに生きてきた歴史、そして文化を越えて響き合う美の言葉—に触れているのかもしれません。

画像出所:メトロポリタン美術館
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)





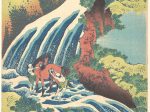
この記事へのコメントはありません。