【日傘の貴婦人図皿(Dish Depicting Lady with a Parasol)】伊万里焼ー江戸時代ーメトロポリタン美術館所蔵

「日傘の貴婦人図皿(ひがさのきふじんずざら)」
日傘の貴婦人図皿──伊万里焼に映る江戸と異国のまなざし
静かな器に語らせる、世界の物語
ニューヨークのメトロポリタン美術館。その一角に、ひっそりとたたずむ一枚の磁器皿があります。直径23.9センチ、高さ2.5センチと、手のひらに収まるほどの大きさ。その表面には、日傘をさし優雅に佇む着物姿の貴婦人が、淡い色彩で静かに描かれています。
この作品は、「日傘の貴婦人図皿」と名付けられた江戸時代の伊万里焼。単なる日用品のようにも見えますが、その背後には、日本とオランダ、中国を結ぶ文化交流の豊かな物語が秘められています。
西洋の空想が、東洋の地をめぐって形を変え、日本の工芸として結実し、ふたたび西洋の美術館に収められる――この一枚には、18世紀の国際感覚、そして日本の美意識の粋が宿っています。本稿では、この「日傘の貴婦人図皿」を中心に、伊万里焼の魅力や背景にある歴史的文脈を、できるだけわかりやすくご紹介します。
伊万里焼とは何か──世界へ向けた江戸のやきもの
「伊万里焼(いまりやき)」とは、現在の佐賀県有田町を中心に生産された磁器の総称です。江戸時代初期、朝鮮陶工の技術によって始まった日本の磁器生産は、有田の地で大きく発展し、近隣の港町・伊万里から積み出されたことから「伊万里焼」と呼ばれるようになりました。
伊万里焼の特徴は、その堅牢さと色彩豊かな絵付け技術にあります。とくに「色絵伊万里」と呼ばれる様式では、コバルトブルーの下絵に加え、赤・緑・黄・金などの上絵が施され、華やかで気品ある作品が多数生み出されました。
17世紀後半から18世紀にかけて、日本は中国の磁器生産が一時停滞したことに乗じて、ヨーロッパ向けに大量の伊万里焼を輸出するようになります。この輸出用伊万里には、ヨーロッパ人の嗜好に合わせた図柄や形状が意識的に取り入れられ、日本の美術工芸が国際市場の中で柔軟に進化していく様子がうかがえます。
「日傘の貴婦人図皿」も、そうした異文化交流の産物の一つです。
日傘の貴婦人とは誰か──西洋の空想と東洋の翻訳
皿の中央には、日傘を差した女性が二人、風景の中に佇む姿が描かれています。彼女たちはいずれも和装の貴婦人で、控えめな表情を湛えながら、視線の先にいる数羽の鳥を見つめています。背景には簡略化された庭園のような空間があり、全体に柔らかく抑えた色調と、緻密な筆致が際立っています。
この女性たちは、単なる日本の風俗描写ではありません。実はその原型は、オランダ人画家コルネリス・プロンク(1691–1759)によって描かれたデザインに基づいているのです。
18世紀初頭、オランダ東インド会社(VOC)は、東洋における磁器生産に対して、よりヨーロッパの趣味に適した製品を求めていました。そのため、プロンクのような画家に装飾図案を依頼し、中国の景徳鎮の工房にその図案を送って生産させたのです。プロンクが描いたのは、理想化された「中国婦人」の姿──つまり、当時のヨーロッパ人が思い描いた「東洋の女性像」でした。
この図案はやがて日本にも伝わり、日本の職人たちはそのイメージを「和風」に翻訳し直しました。中国風の衣装をまとう女性たちは、日本の着物姿に変わり、風景もより日本的に。そうしてできあがったのが「日傘の貴婦人図皿」なのです。
図像と構成──静けさと対話の美
皿の構成は、中心の貴婦人たちの場面を囲むように、内側には花唐草のような文様が配され、さらに外縁には鳥や女性たちが描かれた小さなパネルが放射状に並んでいます。
このような構成は、視線を中央に導く効果を持ち、皿全体にリズムと秩序を与えています。また、コバルトブルーによる下絵付けと、赤・黄・緑の上絵付けが重なり、華やかさの中に落ち着いた気品が漂います。
特筆すべきは、描かれた女性たちの佇まいです。彼女たちは、何かを語ることなく、ただ鳥たちを見つめているだけのように見えます。しかし、その表情や姿勢には、まるで何かを待っているような静かな緊張感があります。そこには、物語を語らずして語る──江戸絵画の伝統とも通じる、象徴的な表現の美が宿っています。
輸出と私貿易──皿が海を越える旅
プロンクのデザインに基づいた中国製磁器は、オランダ東インド会社の公式ルートでヨーロッパに輸出されましたが、日本の伊万里焼による「日傘の貴婦人図皿」は、東インド会社の正式な輸出品ではなく、私貿易(プライベート・トレード)によって流通したと考えられています。
このことは、江戸時代の日本の職人たちが、海外市場の動向を的確に把握し、自律的に商品を開発していたことを物語ります。図案をただ模倣するのではなく、時に大胆に、時に繊細にアレンジを加えながら、独自の工芸美へと昇華させたのです。
それはまた、日本の陶磁器が国際的な競争の中で、いかにして「選ばれる存在」であり続けたかということを示す証でもあります。
美術館に収まるということ──再評価される工芸
こうして制作された皿が、現在メトロポリタン美術館という世界的な美術機関に所蔵されていることには、大きな意味があります。
かつて日常の器として、あるいは輸出品として作られた伊万里焼が、今では芸術品として展示され、多くの来館者の眼差しを受けている。そこには、時代と空間を越えた美の価値があると同時に、工芸というジャンルの再評価も見て取れます。
工芸品はしばしば「使うためのもの」として扱われがちですが、「日傘の貴婦人図皿」は、単に美しいだけでなく、東西の想像力と技術が交差する一点として、芸術的にも歴史的にも極めて重要な存在なのです。
結びにかえて──皿に託された異文化理解
「日傘の貴婦人図皿」は、静かで控えめな器です。色彩も構図も、目立つものではありません。しかし、その一枚にこめられた物語は、18世紀という時代における国際的な想像力の交差点として、限りなく豊かです。
オランダ人が描いた理想の東洋像が、中国を経て日本に渡り、日本の職人の手で再構築され、ふたたび西洋へと戻っていく。この往還のなかで、イメージは翻訳され、形は変化し、そして新たな意味を獲得していきました。
日傘の貴婦人たちは、今も変わらぬ姿で静かに皿の中に立ち続けています。そして、私たちにそっと語りかけてきます。
「異なる文化も、心で見れば美しく重なる」と──。

画像出所:メトロポリタン美術館



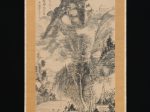


最近のコメント